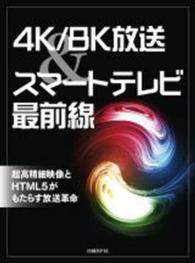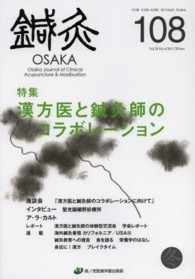感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
98
直木賞】昭和19年11月16日、朝鮮の麗水湾からフィリピンに向かうヒ八一船団の護衛艦大東の副官梶井。12ノットで走る。「門司に帰ったのは大東、鵜来、27号海防鑑の三雙のみ」。敷設鑑常磐、梶井中尉は石油がなく、鉄がなく、輸送路がなくなっていく事実を見る。「死に場所」を捜している海軍。敵の磁気機雷。大尉になり哨戒特務艇、敗戦後の試航船。主題が理解しかけ。戦線が傾いたところで、主戦場ではないところを記述し歴史を掘り起こしている。「戦後掃海事業で死んだ者77人。その顕彰碑は香川県琴平町金比羅宮本殿下の広場」2014/08/17
hit4papa
42
大東亜戦争の末期、「機雷」にスポットを当て日本の敗戦の側面をあぶり出した作品。主人公は、海軍兵学校を出たものの病のため前線での戦いに乗り遅れたいち中尉(後に大尉)。死に場所を求めるものの与えられた任務は機雷の敷設、掃海です。主人公は、機雷のあり様に自身の不遇を重ね合わせ、徐々に機雷に魅入られていきます。本作品は、堅苦しい文体の上に、時折引用される歴史書のような文語体に読書が捗りません。派手な戦闘で語られることの多い戦記ものには著わされない知られざる一面であり、機雷の機構を含め興味を惹かれました。【直木賞】2024/05/24
すーさん
2
濃厚な末期戦の絶望感がよく描写されていた。敵方のほうが2重3重にも上手であるという現実の前の挫折感、そういう中での掃海作業。精一杯の創意工夫も蟷螂の斧、という状況をこれでもかと。
Tatsu
2
駆逐艦に乗っていた海軍兵学校出身の海軍士官が海防艦から機雷敷設艦、掃海部隊へと異動していくにつれ兵器としての「機雷」に興味をもち、のめりこんでいくさまを描いた力作です。著者の光岡明はこの本で直木賞を受賞しました。どんどん機雷にのめりこんでいき、最後は機雷掃海の鬼と呼ばれるようになり、敗戦を迎えたあとも掃海作業に従事する様は、この後の朝鮮戦争における日本掃海部隊の出動へとつながっていったことを想像させます。
Blacky
1
ブックオフ100円コーナーで直木賞受賞帯で興味をもち購入。 この小説購入後、吉村昭など戦争モノ乱読2017/06/18
-

- 洋書
- Tilde