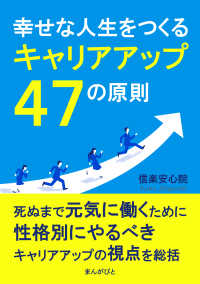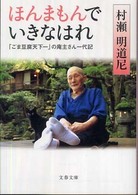出版社内容情報
「考え方の枠組」を表す言葉の本当の意味。 クーンが「発明」し流行語となった「パラダイム」。科学革命は知の連続的進歩ではなくパラダイムの転換によって起こるとする常識破りの新概念を面白く丁寧に解説
第1章 <科学>殺人事件
第2章 科学のアイデンティティ
第3章 偶像破壊者クーンの登場
第4章 『科学革命の構造』の構造
第5章 パラダイム論争――<科学>殺人事件の法廷
第6章 パラダイム論争の行方
野家 啓一[ノエ ケイイチ]
著・文・その他
内容説明
著書『科学革命の構造』によってそれまでの科学史の常識に異を唱えたトーマス・S.クーン。特に「研究者の共同体にモデルとなる問題や解法を提供する一般的に認められた科学的業績」という意味で用いられた言葉「パラダイム」が与えた影響は大きい。具体的史料に依拠し考古学的手法で「知の連続的進歩」という通念を覆した、クーンの新概念を解説。
目次
プロローグ 極私的「パラダイム」論
第1章 “科学”殺人事件
第2章 科学のアイデンティティ
第3章 偶像破壊者クーンの登場
第4章 『科学革命の構造』の構造
第5章 パラダイム論争―“科学”殺人事件の法廷
第6章 パラダイム論争の行方
エピローグ クーン追悼―生き返った科学
著者等紹介
野家啓一[ノエケイイチ]
1949年宮城県生まれ。東京大学大学院博士課程中退。現在、東北大学理事・附属図書館長・大学院文学研究科教授。専攻は科学哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
42
本書はクーンの思想と生涯を紹介した本を文庫化したものですが、パラダイムという言葉を学ぶためには最適だと思います。第5章までは科学殺人事件の容疑がクーンに掛かり、その容疑事実、検事からの尋問、クーンによる弁論と法廷を擬した判決を下すのは裁判長ポパーという落ちになっています。第6章はまとめのようになっていますが、実はこの章の議論が示唆に富んでいると思います。前半ではポパーとクーンの両者の思想は決して対立するものではないという議論がなされています。後半では、批判され半ばクーン自身が使わなくなったパラダイムという2022/03/26
逆丸カツハ
33
英語や中国語の間では翻訳は世界そのものを介して、互いの差異と同一性を比べ翻訳できる。生活世界では世界は自明なものとして導入できるから。しかし、科学は異なる。科学のパラダイムは世界そのものを解明されるべきものとして対象化する。それを媒介して共通性を生むべきものが謎となってしまう。ここに問題がありそうな気がする。2025/12/14
空虚
15
①拡大解釈され世に流通する「パラダイム(・シフト)」という言葉が持ち得る爆発的なイメージに比べて、クーンが用いた「パラダイム」の原義は、一見すると地味なものであるが、科学の現場に根ざしたものだ。例えばパラダイムという概念と不可分の関係にある「通常科学」は、ある科学的業績に依拠する特定の科学者共同体の内部で行われる研究を意味する。その内部では科学者達は語学の学生が文法を学ぶように、教科書的に模範例を学び訓練する。だからといってクーンは、科学の創造性やその進化を否定するのではない。むしろその逆だ。2016/05/07
Olive
11
野家先生、クーンの理論に寄り過ぎ。 中立的立場から見るには注意が必要な本。 でも面白かった。 〈科学〉に対する殺人容疑を裁判に見立てる5章が特に面白い。もちろん被告人クーンと裁判長はポパーだ。2022/10/07
ハチアカデミー
7
いまではすっかり言葉として定着した「パラダイム」という概念を、最初に提示したクーンの意図にそう形で解説した一冊。科学史の研究者であったクーンは、科学が「発展」をする過程で、知識の土台が大きく変わる時期があることに着眼し、特定の時代に特定の集団が共有する前提をパラダイムと呼び、その変化をパラダイム・チェンジと表現する。その言葉の力は、科学史へのみならず、知識そのものへとインパクトを与える。コスモスの解体、ロゴスの解体は、人類の世界認識のありようの見え方まで変えてしまったのだ。ゲシュタルト・チェンジ、辞書…2014/10/01