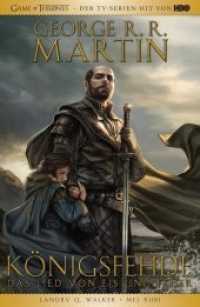内容説明
政変の相次ぐ八世紀後半、孤独で病身の称徳天皇は看病禅師の道鏡と出会う。二人は、称徳が仏教へ傾倒するとともに親密さを増し、孤立し、やがて宇佐八幡神託事件を引き起こした。正統の嫡糸が皇位を継ぐことにこだわっていた称徳が、皇統外の道鏡に皇位を譲ろうとしたのは何故なのか。悪名高き僧・道鏡の真の姿と、悩み深き女帝称徳の心中に迫り、空前絶後の関係を暴き出す。
目次
序章 女帝の系譜を軸とした前史
第1章 看病禅師と女帝
第2章 大臣禅師から法王へ
第3章 宇佐八幡大神の神託事件
第4章 終末の一年
終章 光仁・桓武父子王朝への転換
著者等紹介
北山茂夫[キタヤマシゲオ]
1909‐84。東京大学文学部国史学科卒業。元立命館大学教授。専攻は日本古代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
27
1969年初出。女帝は、道鏡の生地に、巨費と膨大な労働力を投じ、新都を営んだ(13頁)。柿本人麻呂の楽天的高朗性にたいして、人生とは何ぞやという問いを内に蔵した大伴旅人、山上憶良の苦渋をたたえた作風(27頁)。女帝は夫がいない特殊な人間で、寂寥には切実なものがあったにちがいない(49頁)。道鏡は成りあがり者のコンプレックスがあり、セックスの関係で女帝となれあってしまっているので、色恋の沙汰は、伝統観念に挑むまでかれらをかりたてたのである(144頁)。何やってるこんだかね。2015/09/01
おMP夫人
9
国を乗っ取ろうとした悪人。という印象の強い奈良時代の僧、道鏡とその周辺に焦点を当てた本です。本文は固有名詞以外にも馴染みの薄い漢字や単語がたびたび使われ、逆に平易な漢字がひらがなで書かれていたりして少し読みづらく、また、一次史料の少なさゆえ仕方ないのかもしれませんが、謎の多い道鏡という人物を覆うベールは結局のところ晴れないのですが、彼が法王となった時代に行われた政策は仏教色が弱く、むしろ儒教的であったという指摘など意外な記述が多く、興味深く読めました。ただし、ある程度の予備知識が必要かもしれません。2012/06/28
sibasiba
7
やっぱ称徳天皇嫌いだ。道鏡は本当に脇役でこんなもんなのかと肩透かし、何もしてないよ。日本仏教に何らかの新しい展開を、とかもなさそうで単なる成り上がりの小物じゃないか。宗教人としては行基の方が格段上。読み終わっての感想は仲麻呂は偉かったという程度。読みやすいので称徳天皇と道鏡について知りたかったらオススメ。2013/10/20
瑞江 蕾羅
1
古代史の課題で読んだ 登場人物が多くて難しかった2021/07/24
Tokujing
1
久々に古代史の本を読んだ。孝徳天皇と道鏡をめぐる奈良時代の歴史を、北山茂夫独特の物語のような叙述で描いた古典的名著。おそらく孝徳帝と道鏡をめぐる諸問題の中で、宇佐八幡宮神託事件は、日本における王権のあり方の大きな画期となったという意味で、古代史の重要な事件だったと思われる。すなわち日本の王権は天皇家の血統のみを正統とし、臣下はあくまでもその王権の権威に依拠するという、その後の日本の朝廷政治でも基本となる路線の端緒だったのだと思われる。2013/03/09
-
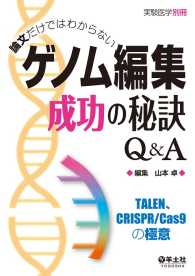
- 電子書籍
- 論文だけではわからない ゲノム編集成功…
-

- 和書
- Anjoのしくみ