内容説明
世界には様々な法体制が併存する。それらは相互に影響しあい形成されてきた。本書は西欧法思想を唯一普遍とする認識を見直し、非西欧の法思想にも目を向ける。ローマ法の源流であるユダヤ法、アラブ民族以外にも普及した包容性をもつイスラム法、一元的原理がなく西欧法移植に成功した日本法。多様な法思想を固有の歴史や文化に絡めて紹介、比較し、西欧法思想の特殊性を炙り出す。
目次
序論 法思想論の現代的課題(戦後における法思想論の展開;法思想論の問題点;現代における法思想比較の問題;比較法思想の分析的道具概念)
第1編 西欧法思想の西欧性(西欧法思想の特徴と歴史;西欧法思想の源流;西欧法思想の成立;西欧法思想の展開;西欧法思想の相対化)
第2編 非西欧法文化の法思想(ユダヤ法思想;イスラム法思想;ヒンドゥー法思想と仏教法思想;中国法思想;日本法思想;固有法思想)
結論 諸法思想の比較的特徴(比較法思想論の方法的課題;現代世界諸法思想の比較的特徴)
著者等紹介
千葉正士[チバマサジ]
1919年生まれ。東北大学大学院法哲学専攻修了。法学博士。東京都立大学教授、東海大学教授を歴任。東京都立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
masabi
16
前著が西欧法思想のみを対象としていた反省から、西欧以外のユダヤ法、イスラーム法、ヒンドゥー法、仏教法思想、中国法、日本法まで扱う。日本でなぜ西欧法を素直に継受できたかといえば、近代化への執着もあるだろうが特定の経典を持つ宗教が定着しなかったためである。古来から宗教と法は表裏一体で生活を監督していた。しかし、日本では中国に範を取った儒教や仏教が日本化され、内在していた法思想も独特の変化を遂げ固有法になった。ある宗教に肩入れするのではなく、現実問題に対応できるものを受け入れる。2015/06/01
那由田 忠
14
長い間積読だったが、やっと読み終えた。西洋の法思想を整理したかった。その点では、法の支配や権利概念の成立についてはっきりしないままに終わった。その代わり、具体的内容が少ないものの、世界の様々な法思想が、本来のこの本の主旨は面白かった。まだ国家が成立しないような、様々な集団において権利義務関係があったという指摘。制裁中心に見るか、互酬性で見てゆくか、権利義務で見るのは後者だろうけど、もっとこの点を追究してほしかった。2020/04/30
Miya
6
法の知識なくして読むには敷居が若干高かったが、プロ倫の解説本は理解の助けとなった。大日本帝国憲法がドイツの憲法を参考に作られたことがその一例であるが、法においても西欧の影響は大きく、著者によれば「西欧法思想は多くの場合に法思想一般と同士されるほど普遍的」であるらしい。西欧法思想が広まっていく過程は、『サピエンス全史』で言及された西洋人の侵略を想起させる。一方、その他の文化と同様に、法においても国や宗教由来の固有法が存在し、固有法と西欧法が融合した形で現代の方は成り立っているそうだ。2020/08/11
1.3manen
5
1986年初出。非西欧の法にも目配りする(裏表紙)。この作法は重要であろう。法思想とは、法体系・法秩序・法文化に関する(35ページ)。哲学は、素朴な感覚・経験や発想・思考を知の理論として体系化すること(51ページ)。イメージ的に法というと冷たさを感じるが、誰のための法か、と問えば具体化してくると思える。中国の法思想は現代の海賊版や著作権侵害はなんとかならないかと思う。財産権とは、社会から公認された物の継続的利用権(270ページ)。アジア世界の法思想まではなんとかフォローできるが、それ以外の地域のルールは?2013/01/07
Haruka Fukuhara
4
勉強になる。2017/06/30
-
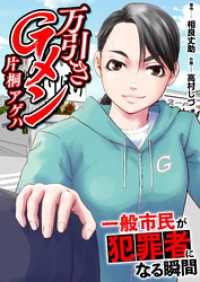
- 電子書籍
- 万引きGメン片桐アゲハ~一般市民が犯罪…
-
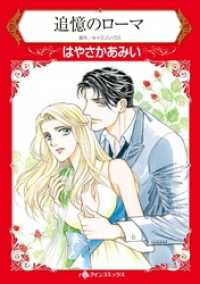
- 電子書籍
- 追憶のローマ【2分冊】 1巻 ハーレク…







