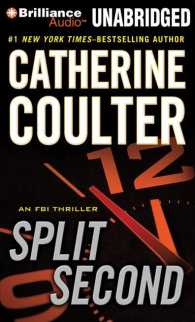内容説明
源頼朝に対抗し、守旧勢力を巧務に操った老獪な“大天狗”。はたまた『梁塵秘抄』を編纂した粋狂な男。後白河がいなければ、天皇制は存続しなかったかもしれない。古代王権を中世王権へと再生させるために、法皇は何を考えていたのか?王権の機能を再編成し、文化情報の収集・独占と操作の意味を透視した天才の精神に迫る。
目次
第1章 後白河論序説(悪左府頼長―偏執と狂気;少納言入道信西―黒衣の宰相の書斎を覗く;法皇後白河―梁塵秘抄・蓮華王院宝蔵・流転の「皇居」;「『人格的靱帯=“縁”のネットワーク』の科学」のためのメモ)
第2章 後白河王権期の都市京都―『方丈記』に見るイメージ(火宅都市;方丈の庵;安元の大火;養和の大飢饉;後白河の新制と都市法)
第3章 中世国家の成立(三つの段階;職と職の体系;中世国家の成立;平氏の台頭;鎌倉幕府の成立)
第4章 『参天台五台山記』―日宋交流史の一断面(成尋の家系;日宋の交通ネットワーク;東アジアの知的交流世界)
著者等紹介
棚橋光男[タナハシミツオ]
1947年山形市生まれ。京都大学文学部卒業、同大学院博士課程単位修得満期退学。文学博士。金沢大学文学部助教授。専攻は日本中世史。1994年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ma3
3
第1章は刺激的な文体で、後白河法皇のカリスマ性を紐解く。第3章では院政期における中世国家の成立過程を描き、鎌倉幕府に結集する領主層の限界性と院・天皇権力の軸を指示した。そして第4章では、この時代の東アジアを舞台にした知的交流の世界を活き活きと描き、日本史という概念がもつ空間範囲を押し広げた。この時代の研究のベースとなる書といえます。2012/11/18
そーだ
0
講談社選書メチエ(1995年)の増補改訂(?)版。解説でだれて一度断念したのをなんとか通読。頼長・信西・鴨長明(『方丈記』)・成尋(『参天台五台山記』)にも言及している。遺稿集にケチを付けるのは心苦しいけれど、なんだかイマイチな本。それともこの本を理解するには自分の知識が足りないだけだろうか。2012/10/01
-
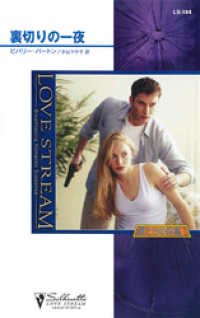
- 電子書籍
- 裏切りの一夜 ハーレクイン