内容説明
人間と金属が織りなす壮大なロマン。西洋に例のない独特の音色をもつ梵鐘はどのように生まれたか。完成まで二十八年を要した奈良の大仏はどうやって作られたか。鋭さと美をあわせもつ日本刀の秘密、また時代を変えた火縄銃、その兵器革命はいかに展開したか―。歴史を創った日本人と冶金技術の興味深い関係を、金属学の泰斗が平易な文章で綴る。
目次
原始の生活
草薙剣
古代における鋳造と冶金
鉄を作る
歴史の中から
鐘の作り方
奈良の大仏
刀の歴史
日本刀を作る
冶金の状況
鉄砲とその製造の歴史
鎖国の間に
飛躍と停滞
日本製鉄工業の夜明け
著者等紹介
桶谷繁雄[オケタニシゲオ]
1910~83。東京大学冶金学科卒業。工学博士。東京工業大学・京都産業大学で教授を歴任、東京工業大学名誉教授。専攻は金属結晶学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まさにい
9
足尾銅山や釜石の鉄鉱石は、江戸時代からあったのだなぁ。全く知らなかった。足尾銅山鉱毒事件が明治時代に問題になって、てっきり明治維新で開発されたものだと思っていた。また、釜石の鉄鋼も、もっと新しいものだと思っていた。古代の鉄については、書かれたのが1965年なので、その後、考古学の分野が進んできたことを考えると、再検証をしなければならないが、面白かった。鉄という金属が人に与えてきた影響を考えると面白い。2024/04/04
くまきん
2
まず、この本の著者は金属の専門家であって歴史については深く研究していない。それは神功皇后の三韓征伐をそのまんま真実として捉えていることで良くわかる。しかしながら我々のような鉄の素人にとっては、鉄の製造の基本とその歴史の流れについて一から教えてくれる良いテキストである。だが、肝心の「鉄製農機具」についは全く触れていない。製鉄技術の最大の成果は農機具にある。2015/03/20
ほしみ
2
冶金・金属学についてはまったく無知だったけど楽しめた。炭素量の僅かな違いとか純度の重要さがよく分かる。2012/08/02
Spark Caretta
1
文庫は2006年だけど元は1965年発行らしい・・・ 日本刀を作るときに叩きまくるのは質を均一にするため 火縄銃が伝わった時すぐにコピーが出来たのは刀鍛冶の技術力があったから 幕末に各藩が必死になって作ろうとしていた反射炉は鉄が炭素と結びつかないよう燃料と原料を分けて炎を天井で反射させて原料を溶かす仕組み 幕末には日本の鉱山はほとんど廃鉱だった・・・深く掘らなくてはならなくなり空気の入れ替えや水対策が大変となっていたなど知らなかったことがいっぱい。2013/07/01
cagliostro_alch
0
原本は1965年刊だが古さは感じない文章。日本の金属史をコンパクトにまとめた良著。2017/09/05
-
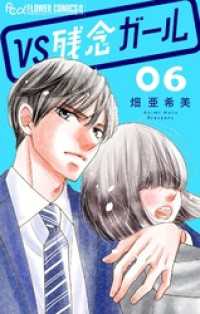
- 電子書籍
- VS残念ガール【マイクロ】(6) フラ…
-
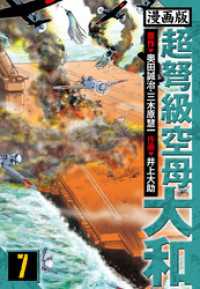
- 電子書籍
- 超弩級空母大和 愛蔵版 7 アルト出版




