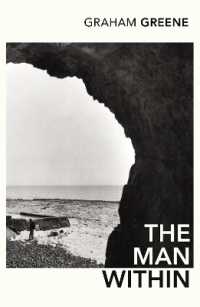出版社内容情報
列島を徹底踏査し、古代文献と格闘。民俗学の巨人による興味深い遺稿の全貌。日本列島を徹底踏査した民俗学の巨人が、『古事記』『日本書紀』『万葉集』『風土記』などの古代文献を読み返し、それらと格闘の末、生まれた日本文化論。稲作を伝えた人びと、倭人の源流、畑作の起源と発展、海洋民と床住居など、東アジア全体を視野に入れた興味深い持論を展開する。長年にわたって各地の民俗を調査した著者ならではの着想を含む遺稿。(講談社学術文庫)
1.日本列島に住んだ人びと
1.エビスたちの列島
2.稲作を伝えた人びと
2.日本文化に見る海洋的性格
1.倭人の源流
2.耽羅・倭・百済の関係
3.北方の文化
4.琉球列島の文化
3.日本における畑作の起源と発展
1.焼畑
2.古代中国の農耕
3.渡来人と農耕
宮本 常一[ミヤモト ツネイチ]
著・文・その他
内容説明
日本列島を徹底踏査した民俗学の巨人が、『古事記』『日本書紀』『万葉集』『風土記』などの古代文献を読み返し、それらと格闘の末、生まれた日本文化論。稲作を伝えた人びと、倭人の源流、畑作の起源と発展、海洋民と床住居など、東アジア全体を視野に入れた興味深い持論を展開する。長年にわたって各地の民俗を調査した著者ならではの着想を含む遺稿。
目次
1 日本列島に住んだ人びと(エビスたちの列島;稲作を伝えた人びと)
2 日本文化に見る海洋的性格(倭人の源流;耽羅・倭・百済の関係;北方の文化;琉球列島の文化)
3 日本における畑作の起源と発展(焼畑;古代中国の農耕;渡来人と農耕)
著者等紹介
宮本常一[ミヤモトツネイチ]
1907年、山口県に生まれる。天王寺師範学校卒。武蔵野美術大学教授。文学博士。日本観光文化研究所所長。1981年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nobi
i-miya
i-miya
i-miya
i-miya
-

- 電子書籍
- 竜の尻尾を噛む二十日鼠【タテヨミ】37話