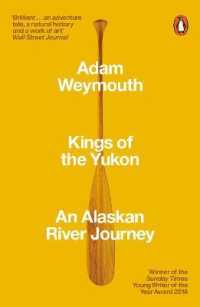内容説明
鉄を制する者が天下を制する。日本の歴史を切り開いてきたものは、大陸伝来の製鉄技術だった。大和朝廷権力の背景にある鉄器。生産力を飛躍的に発展させた鉄製農具。鋳造鍛錬技術の精華、美術工芸品と日本刀。天下の覇者を決した鉄砲。近代国家建設の象徴、官営製鉄所の創業―。考古学・民俗学・技術史を駆使し、“鉄”と日本の二千年を活写する。
目次
鉄器時代のはじまり
大陸からきた鉄器文化
ヤマタノオロチと製鉄民族
大和朝廷をささえた鉄器
三韓遠征と武具
権力の象徴としての鉄器
王朝の確立と製鉄の普及
姿を消した銅製武器
荘園経済をささえた鉄製農工具
鋳鉄技術の発達した鎌倉・室町時代〔ほか〕
著者等紹介
窪田蔵郎[クボタクラオ]
1926年生まれ。明治大学専門部法科卒業。日本鉄鋼連盟に勤務するかたわら、鉄に関する歴史・民俗等の調査を行う。たたら研究会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
15
権力の象徴だった鉄が、農工具のような実用品、さらには武器や工業製品などに大量に使われるようになった歴史を概観できました。輸入した鉄(南蛮鉄)を使って刀を作っていたとは想像したことがありませんでした。2018/08/12
ine
7
鉄を媒体に日本の歴史が世界史の一部に組み込まれていたことを実感。例えばタタラ製鉄。変な名前だなと思ってましたが、なんと語源は中央アジアのタタール族。製鉄は紀元前1300年頃のヒッタイトが起源と言いますが、随分日本まで長い道のりを渡ってきたんですね。日本では元寇などで鉄の需要が高まりましたが供給が追い付かず、各段に生産量が向上するのは、天秤吹子が日本で発明された江戸期。鉄普及の壁は、発明よりも量産化にあったようです。そんな中でも、砂鉄を鍛え日本刀を生み出した日本の創意工夫の底力。製鉄技術は日本の誇りですね。2025/10/01
おかっち
3
鉄って何?と思って読み始めた本。 隕鉄の話から弥生時代の農耕文化とともに日本に入り歴史が始まり、古墳時代の装飾・刀・寺院・大仏・鉄砲・タタラ・反射炉まで(かなり略) いやはや、鉄を辿ると日本の歴史を辿っていけることに驚き。歴史もよく分かっていないため、深く理解することは難しかったけど、訪れた事がある地名が実は鉄の産地だったとか、繋がる部分があり読み進めました。意識すると、今でも鉄から出来ているものは身の回りにたくさんある。自分の暮らしの中にも歴史は詰まりに詰まっている。そこに気づいて考えて学んでいきたい。2018/12/04
まさにい
2
司馬遼太郎の本から、ヤワタノオロチの話は製鉄の話であるということを知り、鉄の歴史について読む。古代の鉄は砂鉄から作るわけだが、子供の頃磁石もないのにどうやって砂鉄を集めたのかと不思議でいた。またヤワタノオロチの神話のころは、それほどの技術がなく、八本の熔鉄の流れがヤワタノオロチであるはずはないと書いてあったが、この八本の流れは、採鉄のための水の流れなのではとこの本から想像をする。この本を読んで何よりも驚いたのは筆者が学者ではなく一般の社会人であることだ。何か三浦シオンの『舟を編む』にも似た情熱を感じた。2016/06/02
影実
1
詳しく書いてある部分とそうでない部分の差が少々気になり、また鉄の素人に対する説明が若干不親切ではないかと思った。着眼点が面白いからなおさら残念に思える。2009/11/20
-

- 電子書籍
- ネイティブの子どもがやっている! ステ…
-
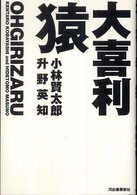
- 和書
- 大喜利猿