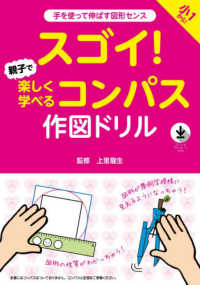内容説明
禅書の古典としてその名も高い『無門関』は、中国南宋の僧・無門慧開が四十八の公案に評唱と頌を配した公案集である。禅の主眼を「無」の一字に見るこの書は、難解なことでも知られる。そこで本書では、『無門関』全文を現代語訳し、公案を易から難への順に並べかえ、平易な解説を付して、より深い理解への一助となるよう試みた。原文・訓読文つき。
目次
『無門関』公案四十八則(どっちがホンモノ(第三十五則倩女離魂)
自己の本来の面目(第二十三則不思善悪)
趙州の無字(第一則趙州無字)
趙州の柏樹子(第三十七則庭前柏樹)
香厳の樹のぼり(第五則香厳上樹) ほか)
『無門関』公案四十八則(原文・訓読文)
著者等紹介
秋月龍〓[アキズキリョウミン]
1921年生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。同大学院修了。花園大学教授を経て、埼玉医科大学名誉教授。1999年9月没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
13
解説や先人の思考を目にしながら公案集を読むなんて本当は何の意味もないのだろうけれど、ぼくは求道に邁進する禅坊主ではなく世俗に染まったボンクラであり、ただただ読み物として『無門関』が好きなだけなので楽しく読めました。答えのない問題と向き合う力を育みながら、その最中にいつか訪れるいわゆるアハ体験的な瞬間の快楽を受け流すことが修行なのだろうけれど(そのためにやっているわけではなくても)単純に個々の公案が生み出された時代背景を確認しながら自分なりの平々凡々なつまらない答えを導き出すだけでもたいそう面白い。2024/01/20
isao_key
8
禅の公案集として知られる『無門関』を解説した書。順序が本来のものではなく、理解しやすい公案から難解なものへと移るように変えてある。解説はあくまで理解への手引きのため、最終的な答えは自分で見つけなさいということらしい。「一切衆生、悉有仏性」(すべての生きとし生けるものに皆物性がある)というのが釈尊の大宣言であり、大乗仏教の根本思想だという。鈴木大拙師はこのことばを公案参究における知的要素とされ、特に強調されていたとある。付録に公案体系の一部である法身、機関、言詮、難透、向上の語が用例とともに説明されている。2014/01/29
Hiroki Nishizumi
2
なんとなく分かったような気がしていて腑に落ちてない。数回読んだ程度ではダメなんだろうな。古典である以上数十数百回読んで、口にして、だろうな・・・2012/12/07
monotony
2
理屈で考えても理解できない話。禅の公案集。理屈で考えないようにしてたら、理屈で考えなくちゃいけない問題に弱くなった気がする。現代人が本当に身に着けなくちゃいけないのはどっち!?・・・多分どっちもです。大事なのはバランス感覚。と言ったら著者に怒られるかな。2012/09/17
田中AD
1
魂と肉体が分かれたどちらが本物かは禅っぽいい話で好き。あれば与え無ければ奪う、これは意味がわからなかった、でも重要な気がする。2018/03/28