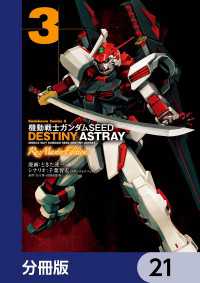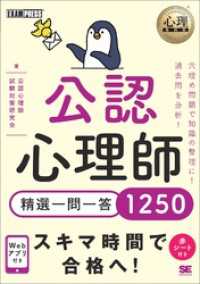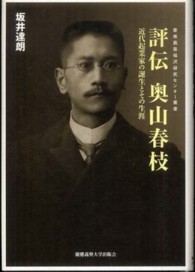感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しお
3
アジア諸社会の成り立ちを深く分析した本。社会形成のための血縁関係、財産継承、共同性(一体感)と排他性の類型化など、異文化を知るための観点がわかりやすく解説される。差別の代表と揶揄されるカースト制度の意義や文化圏の拡大していく考察は大変興味深かった。企業内の役職、親子会社、企業合併、機構改革といった現代社会の組織を考える上で役に立つ。2022/10/15
西東京のハリソンフォード
1
筆者によればこの本の定義は社会人類学の概説書でも紹介書でもなく、社会人類学のもとアジア諸社会を比較考察するものであるらしい。アジア諸社会としては、日中韓インド全般、人のネットワークの話でインドネシア・フィリピン、民族統合例としてマレーシア・シッキムが分析される。前半の社会人類学用語解説は流し読みしたけど、後半のアジア各地域での家族・集団やネットワーク構造の違いの部分が面白かった。中国では科挙があり商人ギルドも実力主義なのに対し、日本は集団内の上下関係や「格」に左右されてしまうという対比が興味深かった。2021/10/01
hal
1
一口に父系社会、母系社会といっても、地域によってかなりのバラエティがあるのね。分析より、この時代に女性ながら、かなりの数のフィールドワークをこなしておられるところに感服した。2018/09/24
MIRACLE
1
社会人類学者である筆者が、インド、中国、韓国、日本、東南アジアの社会構造(=集団のあり方)について、社会人類学の方法論を前半で紹介した上で、比較を試みた本(単行本は1986年刊行)。インドのカースト制であるヴァルナと、ジャティの違いについて、知ることができた。一方、筆者は、社会人類学の分析概念が最も発達しているのは血縁、婚姻に関する分野と述べておきながら、本論でそれを活用していない。そのため、本書は「羊頭狗肉」の印象を与えている。342頁、367頁に誤植がある。2017/02/16
OjohmbonX
1
同著者の『タテ社会の人間関係』は、場と資格の二軸で日本は場重視の社会、って前提からいろんな特徴を説明する話で、途中式の省略が激しくて検証するのが大変だったので、ひょっとして本書はその辺他のアジア諸国とも対比しながら詳細に論じてるのかもと思って読んでみたけど、そういう本じゃなかった。社会人類学ってこういう学問だよって説明と、場/資格の概念にはこだわらずにアジア各国の血縁構造やそこから来る人間関係の感覚を説明してた。もしかすると著者自身が、前提を限定して体系を構築する、というタイプの人じゃないのかもしれない。2016/04/26