内容説明
生命と生物の謎をめぐり、生物学は厖大な発見・論争・誤解を積み重ねてきた。二千年をこえて生きたアリストテレスの観察眼、「子ヒツジのなる木」を信じた中世、「素人」ゆえに法則を発見したメンデル、パスツール・コッホ微生物大論争、そして衝撃的なDNA二重らせんの発見まで。個性的な開拓者たちの人間味あふれるエピソードで綴る生物学の歴史。
目次
生物学発祥期の代表者―プレニウス
「目的論」で貫く自然観―アリストテレス
さまざまな動物寓話―中世の博物学
「実験」学派の祖―アルベルトゥス・マグヌス
ドイツ植物学の父―コンラート・ゲスナー
人体解剖の若き天才―アンドレアス・ヴェサリウス
血液循環の発見者―ウィリアム・ハーヴィー
客観的な顕微鏡家―A.ファン・レーウェンフック
ヤトロ物理学とヤトロ化学
近代的な実験家―ラツァロ・スパランツァニ〔ほか〕
著者等紹介
長野敬[ナガノケイ]
1929年生まれ。東京大学理学部植物学科卒業。専攻は細胞生物学。医学博士。自治医科大学医学部教授を経て、現在同大学名誉教授。河合文化教育研究所主任研究員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
182
30のトピックから業績より、ひととなりにフォーカスしている。 エールリッヒは「夢の人生」とお題の作文で「たぶん夢は、脳の発する燐光のようなものだろう」って、生理現象として書いちゃうの激アツっすね。恐らく脳内物質がまだ知られていない時代。 ポプキンズの論文は、揚げ足を取られることは少ないのですって。ライバルであっても、誤りを批判するより、一緒に考えるのに熱中してしまう。と。誠実な物言いがそうさせるとか。 科学に於いて正しい批判や対抗理論は、発展するために不可欠と理解。でも、違う方法があるって良いですね。2020/02/18
トムトム
16
面白かった!有名な科学者さんのお人柄を記述。ファーブルさんはダーウィンの進化論が嫌い。「進化論は過去と未来の話をしている。今現在、目の前で生きている生物を観察しろ!」。ファーブルさんらしいなぁ。パスツールとファーブルの出会いも面白かった。推測や「だと思う」という長野先生の主観が入っているけれど、それが面白い。科学書でデータの羅列みたいな面白くない本があるけど、本を読むなら著者さんの考えや人柄が出ている方が好き!2020/02/07
さきん
6
生物学の教科書に載っている人の人生と業績が良くわかる。顕微鏡を駆使したレーウェンフックの話などがおもしろい2015/07/08
丁字路
2
生物学の主だった発見について面白おかしくまとめた一冊。その当時にあった偏見や批判の妥当性についても書いてあるのが特に面白い。2017/02/24
-

- 電子書籍
- 婚約破棄された『空気』な私、成り上がり…
-
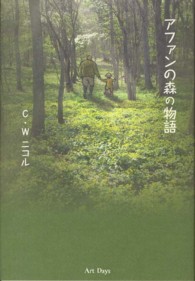
- 和書
- アファンの森の物語







