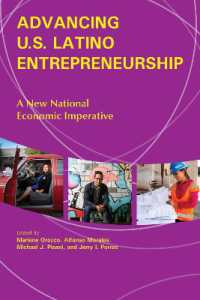内容説明
明治国家における「国体」「近代天皇制」の確立は、“伊勢”=国家神道の勝利であった。その陰で闇に葬られたもう一つの神道・“出雲”。スサノヲやオホクニヌシを主宰神とするこの神学は、復古神道の流れに属しながら、なぜ抹殺されたのか。気鋭の学者が“出雲”という場所をとおし、近代日本のもう一つの思想史を大胆に描く意欲作。
目次
第1部 復古神道における“出雲”(「顕」と「幽」;本居宣長と“出雲”;平田篤胤と“出雲”;篤胤神学の分裂と「幽冥」の継承 ほか)
第2部 埼玉の謎―ある歴史ストーリー(出雲と武蔵;埼玉県の成立と大宮の動向;千家尊福の知事時代―古代出雲の復活)
著者等紹介
原武史[ハラタケシ]
1962年生まれ。東京大学大学院博士課程中退。東京大学社会科学研究所助手、山梨学院大学助教授を経て、現在、明治学院大学助教授。専攻は日本政治思想史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
67
日本書紀に記された短い記述「一書曰」から浮かび上がる幽冥界の支配者としてのオオクニヌシ。本書は江戸時代の国学から発生し、その後神道のもう一つの可能性として存在したそれを丹念に追った一冊。初めてこの思想の存在を知ったのは折口信夫に関する著作でその時は彼に関する部分しか記されていなかったのだが、こうして時代ごとに書かれているとその発生から国家神道に収斂されるまで、地下水脈の如く正当に対するカウンターとして存在していたのが良くわかる。明治維新がある意味宗教戦争だという事が良くわかる一冊で、必読の一冊かな。2023/10/17
やいっち
33
十数年前に読了していた。感想は書いてない?
ころこ
32
近代化のために「国体」という全体主義の文脈で使われた日本思想の中にある対抗思想の歴史を紐解くことで、ステレオタイプに陥りがちな日本思想に別の可能性を発見します。梅原猛、井沢元彦の仕事に似ていますが、彼らとは違い、文章を読み解釈するという地味ですが、実証的でアカデミックな態度を貫きます。オホクニヌシの思想が怨霊信仰だとは言っておらず、展開不足の印象です。日本人の欠点ともいえる優しさや決断力の無さは、見方を変えればリベラリズムの原点だと展開すれば、本としては読み易くなりますが、「こう思う」を抑制して論を進めま2020/04/26
ゆう
30
明治維新成立時にイデオロギーから切り捨てられた神道、「出雲」の系譜について論じた本。国家神道が宗教ではないこと、権力の継承を一本化するために切り捨てられた神々が存在することが、平田篤胤の思想、特に「日本書紀一書第二」の解釈に基づいて考察される。本書を読みながら思いめぐらせたのは、明治維新が成立する前の民間信仰についてだ。宗教がない為に、日本人には道徳性や倫理性を担保する仕組みがないという言説を度々目にするが、出雲の神々が担っていたのはそのような規範性ではなかったか。「幽冥」の概念は今どこにあるのだろう。2020/04/12
いいほんさがそ@蔵書の再整理中【0.00%完了】
28
**日本神話**神話・天皇ネタの小説読解の為読了。<出雲>はなぜ明治政府に抹殺されたのか?「国家神道」「国体」の確立は、<出雲>に対する<伊勢>の勝利で決した。歴史の闇に葬られたオホクニヌシを主祭神とするもう一つの神道思想の系譜に大胆に迫る!?――本書が事実か否かは別として、目に見える世界を司るアマテラス(伊勢の祭神・皇室の祖神)。目に見えない世界を司るオホクニヌシ(出雲の祭神)。本来は別物である2つの神話大系(システム)を対立させる事無く日本に定着させる試みであった平田篤胤などの神道思想。 ⇒続き2013/09/03