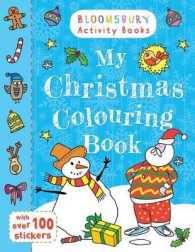内容説明
1815年、八十三歳の杉田玄白は蘭学の草創から隆盛に至るまでを思いを込めて書き綴った。『解体新書』公刊の苦心や刊行後の蘭学界の様々な動向など、まさにその現場に身を置いた者ならではの臨場感あふれる筆致は迫力に満ちている。初めて「長崎本」を用いて、現代語訳・原文、さらに詳細な解説を付した、文庫オリジナル版全訳注。
目次
現代語訳
原文
解説(『蘭学事始』執筆の目的と著作の意義;「蘭学事始」「蘭東事始」「和蘭事始」;底本『蘭東事始』;古写本とその分類 ほか)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
駄目男
19
オランダの解剖学書『ターヘル・アナトミア』の日本語訳『解体新書』を世に出すために、前野良沢、中川淳庵、杉田玄白が、ああでもないこうでもないと知恵を出しつつ、翻訳していくわけだが、吉村昭の『冬の鷹』を読むと、主幹翻訳者は杉田玄白ではなく前野良沢だということだ。その翻訳作業の困難を記したのが杉田玄白が晩年に書いた回想録『蘭学事始』ということになる。「一滴の油これを広き地水の内に点ずれハ散して満池に及ふとや」三人で申し合わせ、仮初に思ひ付きし事、五十年近き年月を経て、此学海内に及びと回顧している。2025/07/22
gill
15
読みやすい現代語役でするすると読めました.杉田玄白,や解体新書といった名前や蘭学のことは歴史の教科書で中学生の頃に少し覚えましたが,本人の筆致で綴られた蘭学の発展や医学への熱意に基づくターヘル・アナトミア翻訳への情熱はとても有機的で,学校で習ったこととはまた違うリアルタイム感あふれる視点を与えてくれました.本人も最後に記していますが,自分達の始めた蘭学が世に広まって浸透するまでを生きているうちに見られたことは幸せなことでしょうね.色々な人の熱い志が垣間見れて,とても良い刺激になる1冊でした.2015/08/01
Ryoichi Ito
8
ターヘル・アナトミアの翻訳事情,その後の蘭学の発展を記す。巻末に曰く。「八十三齢,九幸翁,漫書す」大仕事をなし,長寿を全うした幸せな一生だった。本書は原文と現代語訳。読みやすい。オランダ語からの翻訳は前野良沢が主に担当し,漢文体に直す作業は杉田玄白が担当した。翻訳の具体的な方法は本書には記されていないが,前野の別の資料から,次のようになされたらしい。原文の各語を漢語に直し,全体を漢文訓読方式にならって日本語に読み下す。これを漢文に書き換えるのは漢文に精通した杉田玄白にはそれほど難しくなかったことであろう。2018/07/23
Hiroshi
7
上下2巻からなる杉田玄白の回顧録を現代語版で1冊にしたもの。江戸時代は、初めのうち横文字を使うことは許されなかった。8代将軍吉宗の時、オランダ通詞3人が通訳なのにオランダ語を知らないのは辛いと言った。吉宗はもっとなことだといった。オランダ人が渡来して100年余り経って、横文字を使うことが許された。吉宗は、日本や中国の書物にはない図の精妙なものがあり、この本に書かれていることを読むことができたならば、きっと細かいことまで役立つであろうと言われ、江戸で誰でも蘭語を学べるようになった。これが蘭学の始まりである。2019/04/30
藤井宏
5
現代語訳の部分のみ読んだ。アルファベットも知らないのに、オランダ語の本の解剖図の正確性に感銘を受け、手探りで翻訳していく。鼻の記載で、verheffendという言葉が書いてあって、庭掃除をした時、塵が集まって、verheffendすることから、「うずたかくなる」の意味だろうと推測する様子には、それだけでも苦労がわかる。事実かはわからないが、司馬遼太郎の「菜の花の沖」で、高田屋嘉兵衛がロシアに連れて行かれたとき、ロシア語を習う様子を思い出した。「草葉の陰」と呼ばれたエピソードには笑った。2018/01/12
-

- 洋書
- ÉlÅ