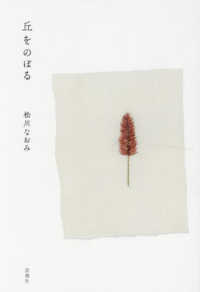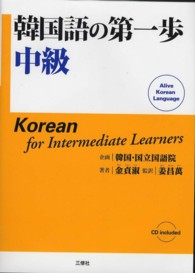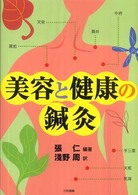内容説明
武士道の聖典ともいわれてきた『葉隠』には、なぜか「殉死」の語はなく、すべて「追腹」であり、「武士」の語の多くが「奉公人」に変えられている。また『葉隠』の存在は、実は江戸時代を通じて秘せられてきた…。山本常朝の生い立ちと思想を深く読み込むことによってこれらの謎を解き、さらに、通説を大胆に問い直した著者会心の力作。
目次
序章 『葉隠』と山本常朝
第1章 奉公哲学
第2章 曲者列伝
第3章 家老論
第4章 没我的忠誠
第5章 傑僧外伝
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
30
死を強調しているイメージがありますが、内容はそうとはいえず、かなり人生訓てしてまとめられていると思います。書かれた当時と時代が異なっても今に通じる話が多いので参考になりました。2023/05/16
加納恭史
18
遠戚の者が出演しているので、一応映画「国宝」を見た。人気が続く。三島由紀夫の葉隠入門を確認しようとこの本を読む。三島由紀夫の解釈はおおむね正しい。葉隠は江戸時代の中期の作品である。もはや合戦はなく太平の世であった。「殉死」の言葉はなく、「追腹」である。その少し前までは君主の命令は絶対であった。切腹もあった。少し読むと、武士の歴史的な訓戒が多い内容。武士道の心得は「奉公人」に変えられている。君主への奉公人の忠誠がテーマになっている。やはり新渡戸稲造の「武士道」と同様に論語・孟子・朱子学の忠誠が主題である。2025/09/26
kawamata
17
江戸時代中期に武士の心得を書いた『葉隠』を解説した本。『葉隠』は佐賀鍋島藩士・山本常朝の語りを、田代陣基が書き留めたものとされる。サラリーマン化した当時の武士に、武士としての心の在り方を説いている。「死ぐるい」「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」など、一見『死』を美化しているようにも思えるが、実は自分の生死より『大切なものを見失うな』とか、死を恐れるあまり『自分のなすべきことを怠るな』とかの意味合いが強い。葉隠が正道だったのかは疑問だが、自分が何を最も大切にして生きていくかは見失わないようにしていきたい。2017/08/15
加納恭史
13
映画「国宝」が面白かったので、小説「国宝(上)」も読んでみる。映画と少し違う面もある。葉隠も二、三冊読んだが、何と言ってもこの本が秀逸のよう。半ほどの家老論が特に素晴らしい。太平の世の中で武辺の武士道から役人の奉公人としての武士道への転換が独特です。その中心は君主または藩への忠誠心である。著者の常朝は大変な博識である。論語・孟子・朱子学での奉公人の忠義心が厚い。その圧巻は家老論である。君主を諌める諫言のやり方をこと細かに述べている。有能な君主と無能な君主への対応は異なる。無能な君主への対応は涙ぐましい。2025/09/29
monotony
6
「葉隠」そのものを読んでみたくて、タイトルと出版社を信頼して買ったのだが失敗。葉隠の一部を引用しながら著者の解釈・解説を加えるというスタイルのため、葉隠そのものが読める本ではありませんでした。一応は目を通してみたけど途中で疲れました。この本は別の本で全体像を把握してから読むほうがいいと思います。最初の一冊では無かった。。。2016/01/30