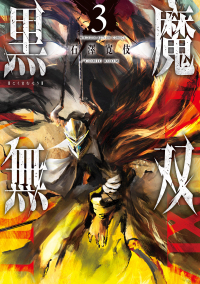内容説明
フロイトに共鳴したヴァイツゼッカーは、内科学に精神分析を導入するという野心的な試みを行ない、独自の心身相関論を構築した。デカルト以来の心身二元論と、心身両者間の単線的な因果性を徹低的に排除し、心と身体が相互に原因と結果となって、円環の関係で一体となると主張する。発病を人生のドラマ、生活史のドラマと捉える観点の必要性を説いた画期的研究の初訳成る。待望の文庫オリジナル。
目次
1 ドラマ、その内容と形式面。興奮の移動。性と道徳性の役割。―扁桃炎
2 歴史性。いわゆる心因性。主体の導入。機能障害の分析。両価性と拮抗性。―尿崩症
3 悪循環。症状の発生。ある人物への結びつきの意味。―発作性頻脈
4 ヒステリー性麻痺
5 複視
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
4
解説にて著書の両面を指摘する。「ユダヤ人の友人をもつ彼がナチスの反シオニズムを容認することはそれ自体大きな自己矛盾だった…ヒットラーが政権を掌握するとともに…自分の助手でナチ党員でもあったヨハネス・シュタインの要求に屈して、敬愛するフロイトの著書『幻想の未来』を焚書のリストに入れることに賛成したのである。…しかしその一方で、彼は神経科の図書室にフロイト全集を揃えるという形でナチスに対する反抗も示していた。しかし…「全体のための個の犠牲」という名目でナチスのホロコーストにー一時的であるにせよー同調している」2023/10/16
中山りの
0
主体としての患者や医師、生活史、心、身体、それらの円環的な関係性。ダイナミックな動き•関係性に着目して病因を捉えようとすることが大切。 単純な因果論的に一方通行の矢印を引くだけでは見落としてしまうことがある。2013/05/04
-

- 洋書
- Hands Up !