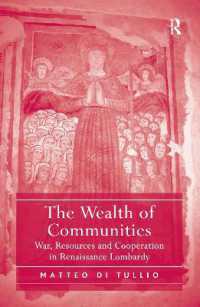内容説明
近代の哲学は、身体の問題を奇妙に無視してきた。しかし、人間の現実存在は、身体をはなれてはありえない。身体であるということが、人間が単に考えうる可能的存在ではなく、現実的存在であるゆえんをなしているからである。本書では、こうした観点から、身体をポジティブなものとしてとらえ、人間的現実を、心身合一においてはたらく具体的身体の基底から、一貫して理解することをめざしている。
目次
身体の現象学
第1章 現象としての身体(主体としての身体;客体としての身体;私にとっての私の対他身体;他者の身体;錯綜体としての身体)
第2章 構造としての身体(はたらきとしての構造;向性的構造;志向的構造;身体の私性;自己と他者;構造の生成;精神としての身体)
第3章 行動の構造(行動と生活世界;癒着的形態の行動;可能的生への展開;可動的形態の行動;シンボル的形態の行動)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
24
著者の思考の出発点となったポール・ヴァレリーのいう「錯綜体」は、私たちが身体についてのあらゆる感覚や概念(心身二元論や心身合一という考え方も含む)を自他に抱くことを可能ならしめている土台となるものと私は理解した。それは精神とか身体とかいう以前に、自分を当たり前のように自分だと了解する上で必要な原初性や統合性、つかみにくさ、逃げ去りの「化身」のようなものであるだろう。つまり、私たちの知らない自身の始まりだ。2021/05/20
yutayonemoto
4
【速読】ヴァレリーの身体論なんてあるのか。身体の現象学。意味は物凄くわかるが、「原理」ではない。原本の初版が昭和50年。前書きの講演録と中村雄二郎さんの解説を見た後にグワッと読めば良い。著者も後書きに書いているが、「媒介され、拡大された社会的身体」の分析が無いのがもったいないオバケ。2016/05/23
左手爆弾
4
「身体論」という言い方も奇妙なものだ。過去の哲学が軽蔑してきた身体(これ、本当だろうか)をもう一度見直し、「生きられた具体的なものとしての身体」を考察するという。だが、「生きられた具体的なもの」は、果たして書物の中の言葉へと入っていけるのであろうか。過去の時代より身体を使わずに生活できる我々が、過去の哲学者を笑ってよいものだろうか。彼らにだって当然、身体への配慮はあっただろうが、それとは違った次元でものを考えているだけではないだろうか。つまり、「身体"論"」として論じる必要はどこにあったのだろうか。2014/08/19
⇄
3
主体の〈私〉は、様々な要素で形成され、そこには他者、私における私の対他存在などを変換することで〈私〉となる。コミュニケーションが発生せずとも共同的な行動における現象は、赤ちゃんの頃から潜在的に存在し、しかし赤ちゃんの頃は、例えば”恥ずかしいから”と赤面しない。いくらなんでも面白すぎる本だった。何日もかけて分けて読んだため、かなり時間がかかった。2023/08/11
NагΑ Насy
2
セミナーで書名を紹介されていて頭にあった本に散歩をしながらふらっと入った古書店でちょうど見つける。この本にあるような、こういう「わたし」の捉え方はベルグソン由来なんだろうか。メルロポンティやらなんやらの影響の下にと解説にはかかれていたけれど。まえがき部分の講演の文章での離人感にまつわるところのエピソードは自分も同じような道筋をむかししていて、ある状況におかれた人間がたどる、あるいみで自然な仕方だったのかもしれない。身体が疎外されていってしまったときの帰結としての離人のくるしみ。2013/01/31
-

- 洋書
- Lübecks Tö…