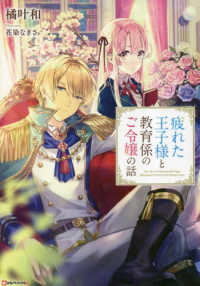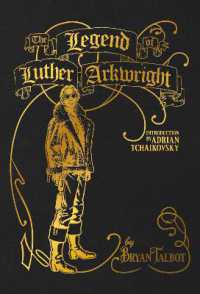出版社内容情報
【内容紹介】
魯迅の弟、周作人に始まる中国の民俗学研究の歴史は浅く、研究方法もいまだ模索の段階にある。本書は「古代文字の構造を通じて考えられる古代人の生活と思惟、古代歌謡としての詩篇の発想と表現とを通じてみられる生活習俗のありかた、そしてそれによってえられたところのものをわが国の古代の民俗的な事実と対応させながら比較」考察するという3つの方法をもって、未開拓の中国民俗学研究という分野に正面から取組んだ労作である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
6
象形・指事・会意の文字は二千字ほど「同時」に作られ、音声的な形声文字はその後作られ始めたという。著者は、形声文字の音声ネットワーク形成後の支配構造を前提とするより、甲骨文や青銅器に刻まれた金文にある形声以前の3種の文字の画に込められた書く行為の呪術面から出発する方が、民俗習慣を「容易に」「復原」できると考える。本書は、日本民俗学の方法を検討しつつ、地霊に対する言霊観念を基盤とする古代歌謡の民俗を『詩経』に見、卜辞に自然観を、語り部に巡遊者に零落した巫史を、そこから歳時や儀礼の制度化の著しい傾向を仮説する。2020/12/14
hachiro86
2
文字から「民俗」を読み解くという方法の驚異2009/07/01
tokumei17794691
1
・本書は、前作『古代中国の文化』との併読を前提にしているようで、『古代中国の文化』も読まぬと分かりづらい。・『万葉集』の引用が多数あることからも、古代日本の民俗・文化との対比が多い。そのため、古代日本の民俗・文化の知識がないとついていきづらい。また、中国のことを言っているのか、日本のことを言っているのか、読んでいて結構混乱した。・「歌謡の原質が、本来呪的なもの」との着眼点は、興味深かった。・「あとがき」が本文の的確な要約になってることは評価する。「あとがき」から先に読んだほうが良い。2021/06/13
amr
1
よく説文解字の話が出てくるけど、こんだけ研究したら1900年も前の許慎に「これ、そうじゃなくてこうじゃろ?」ていう問いかけができるのだなーと思ってなんかおもしろかった。内容とあんまり関係ない感想やけど。2014/07/18
ヴィクトリー
1
「民俗」のありかたを「神との関りにおいて営まれる人間のありかたにほかならない」として、詩経にみられる草摘みなどの行為に予祝的なものを見て、それが万葉集にも同様のものが見られるとして、殷人と古代日本人の間に共通の心情を見いだす。なかなか形にははっきりとは残らないものを扱うだけに文字や詩からの推測になるが、読込みが深いのでとても説得力がある。2012/06/27
-

- 和書
- 長谷寺小池坊能化列伝