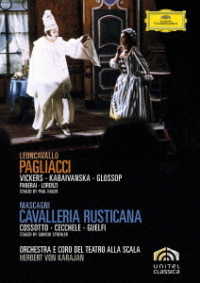出版社内容情報
【内容紹介】
仏教といえは、釈尊を知らない人はいない。だが、本当の釈尊の姿は、どれだけ知られているのだろうか。本書に於て著者は、仏教一すじの長年に亙る思索と研究の中から、釈尊の生涯とその思想においてその眼目をなすといわれる菩提樹下の大覚成就、すなわち、「さとり」こそ、まさしく直観であり、そのさとりは受動的なものであったという結論を導き出した。釈尊の生涯を見つめながら、その真実の姿を明らかにした仏教入門の白眉の書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちさと
43
お釈迦さまは王子様で戦争してたんだけど、あんまりに多くの人が死ぬのでどうしよって悩みまくり、変な人になった。その後出家して何年も苦行したのに悟れず、止めて休憩してたら悟った。こんな知識しかない私にもよく分かる「釈迦入門」。正覚を成就した後も、心細く不安に思ったという所謂「正覚者の孤独」についての疑問が最後にふっと解けました。難しい説法の前に釈迦の悟りのプロセスと完成までを知るにはもってこいの良書です。2019/04/11
KAKAPO
39
>生は苦なり、老は苦なり、病は苦なり、死は苦なり…。貪りの心があると苦が生ずる。渇愛滅すれば苦もまた滅する。渇愛を滅する方法は、正しい見方、身・口・意のいとなみを正しくすること、正しい生き方、正しい修行のいとなみ…。生老病死という、避けられないものがあることを認め、それを受け入れて苦と共に生きる。欲することは得られないことによって、得ることは失うことによって苦に転ずることを認め、貪らないように生きる。自分にこだわると自分の苦が大きくなってしまう。自分へのこだわりを捨てると自分の苦しみが相対的に小さくなる。2019/04/21
ねこさん
26
阿含経典(ちくま学芸文庫)を訳している増谷文雄の講演を起こした、90ページとごく薄い本。しかし、特に「十二縁起」と「八正道」については、今まで読んだどの仏教入門書よりわかりやすく、その入口へ導くように述べられている。「苦」とは何なのか、「苦」はどのように生じているか、この「苦」から離れるためにはどのように「正しく」生きればよいのか、その心身の運用の方法までを釈尊は丁寧に説いた。「苦」に無自覚である人にとっては何の意味も持たないそれを伝えるのは困難だろう。その意味においても、お薦めする相手の見つけにくい本。2019/02/14
おおにし
23
仏教開祖である釈迦がどんな人物であったのかを知るにはもってこいの入門書。説法を始める前の釈迦は、自分が苦労して得たさとりを人に教えるなどまったくするつもりはなかったし、私のさとりはどうせ誰も理解できないだろうと考えていた。さとりは直観なので人に言葉で伝えることは困難だとも思っていたようだ。そんな利己的人間だった釈迦が初転法輪(最初の説法)をするまでの葛藤やためらいが、とても人間的で親しみがもてる。釈迦がどんな説法をしていたのかとても知りたくなった。2018/02/10
ねこさん
19
愁、悲、苦、憂、悩から離れる清廉と、それらに触れていたい切なる欲求があり、生きて成熟してゆくことの妙味が、今ここで同居している。我の深刻はいつか平衡を破り、機を得た融解は最大化する。全身の皮膚は鼓膜のようにふるえ、涌出する生成物は処理しきれない。ただこの事態の重要性の実感に打ちひしがれる。筆者は悟りを直感と言う。人はこの直感を解釈してしまう。悟りたいと欲する人が、どれだけあるんだろう。直感が既に自らに内在しているという前提は救いとして機能する。救いは生きる動機の独なる自覚であって、欲求の成就ではなかった。2019/10/31