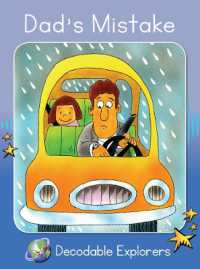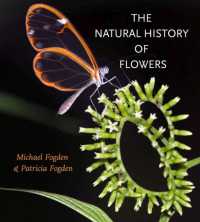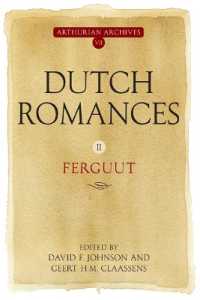出版社内容情報
柳田 國男[ヤナギタ クニオ]
著・文・その他
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
(C17H26O4)
84
妖怪の民俗学というべきか。逸話がぎっしり。ルーツや各地での類似点や相違点などなど。例えばナマハギ。秋田ではナマハゲ。(妖怪?)遡ればナモミハギ。ナモミとは火にあたっていると皮膚に出る模様。東京ではヒガタ。ヒダコ、アマメ。ナモミは北部ではナゴメ。青森ではナマハゲ同様の行事をナゴメタグレ、シカダハギ。面白かったのが、オバケと幽霊の違い。前者は出現場所が決まっているが、後者は追いかけてくる。前者は相手を選ばないが、後者は決まっている。前者は丑満時に出るが後者は宵と暁の薄明かりに出る。らしい。巻末に妖怪名彙あり。2020/07/14
NAO
61
【日本の夏は、怪談 其の三】妖怪談義というから妖怪の話がたくさん語られているのだろうと思って図書館で借りたのだが、妖怪についての様々の解釈が述べられている、いたって真面目な本だった。とはいえ、もちろん、いろんな妖怪が出てくる。その中でも、河童に関する話はなかなかおもしろかった。山姥や山男に関する柳田国男の解釈も、興味深い。2020/08/25
NAO
45
【日本の夏は、怪談 其の三】妖怪談義というから妖怪の話がたくさん語られているのだろうと思って図書館で借りたのだが、妖怪についての様々の解釈が述べられている、いたって真面目な本だった。とはいえ、もちろん、いろんな妖怪が出てくる。その中でも、河童に関する話はなかなかおもしろかった。山姥や山男に関する柳田国男の解釈も、興味深い。2020/08/25
テツ
14
妖怪。未だにその二文字を目にするだけで心躍る。小学生の夏休みに祖母から買って貰った水木しげるの妖怪辞典を延々と読んでいた時代から今に至るまでその手の話が大好き。柳田國男による彼が生きた時代よりほんの少し前の日本の隅々に感じられた妖怪たちの姿と習性の研究。今はもう例えば『本所七不思議』があったという場所も夜中でも明るくなってしまい彼らの姿を幻視することもなかなか一般人では出来ないけれどこうして文章として残されている限り絶滅は決してしない。妖怪は情報と記憶の中に生きる生命体だ。2016/07/24
翔
10
地元の地名が出てきたことに驚き2019/02/26