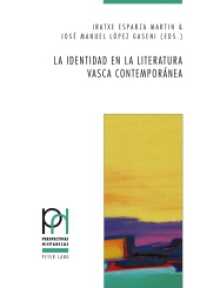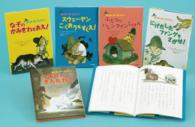出版社内容情報
【内容紹介】
日本人の労働を節づけ生活にリズムを与え、共同体内に連帯感を作り出す季節の行事。本書は、各地に散在するそれらなつかしき年中行事の数々を拾い蒐め、柳田民俗学の叡知で照らした論集である。著者の比類なき学識と直観は、固くむすぼおれた古俗・伝承の糸口を鮮やかに解きほぐし、その成り立ちや隠された意味、また相互の連関を明らかにしていく。芳醇な筆致にのせて読者を日本農民の労働と信仰生活の核心に導きゆく名著である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
9
太陽暦以前の十干十二支を採用した近世をさらに遡ると、供を行う「時折(トッキヨリ)」が読者のそばにあることが感じられる。デジタル化した時間を解きほぐすと、折ることで節目を作る時が出てくる。節句の「句」は元々神に供物を捧げる「供」であり、5節句の区分以前の3節句(供)から時を節目と捉える著者は、節目の時期に人々が集い祖先や神に供物を捧げて飲食を共にする機会を持ったと推測する。正月(神道)やお盆(仏教)の行事の記述が極端に少ない点も民衆の時の観念史を扱う本書の特徴だろう(今の「正月」は中世までなかったという)。2025/02/22
てれまこし
8
今日では、祭の意味は一般人にはほぼ理解できないものになった。まずは明治維新後に、新暦が採用され、神道家により祭がすべて皇室に結びつけられてしまう。これによって民衆の生活から切り離され、農業とのつながりもなくなり季節感も失う。暦上の日付だけが問題となる。第二に、戦後においてこうした国家主義的な祭日が否定され、憲法記念日のような新しい国民の休日が取って代わる。後に保守派の巻き返しにより旧祭日の一部も別名で復活したが、いずれにせよ民衆にとってはピンとこない伝統である。こうなりゃクリスマスでもハロウィーンでもよい2018/10/19
ミツ
4
現代ではもはや失われつつある日本の年中行事に関して、様々な民間伝承に触れつつその本来持つ意味を解き明かしてゆく。 元来稲作農耕と密接に関わりある年中行事だが、それは民間信仰のかたち、人が神とどのように関わっていたかを生き生きと伝えてくれるものである。 研究の基盤である口承によって語り継がれた怪談奇談の類も実に様々で、面白く読んだ。2010/10/15
demoii
2
書かれた当時でも加速的に消えていくことが危惧されていた年中行事。現代に生きる自分には聞いたことも無いような話も多くあった。2011/05/16
塩崎ツトム
1
昔の日本は(今でもそうだけど)眠気を忌むものとしてそれを川に流して払う儀式があるというのは興味深い。仕事中毒の日本人。2013/04/18
-

- 電子書籍
- 十二夜【タテヨミ】第31話 picco…


![[Set Rist: Geistliche Liedsammlungen, 12 Bde.], 12 Teile (2021. 7250 S. 240 mm)](../images/goods/ar/work/imgdatak/31107/3110747863.jpg)