出版社内容情報
アロマとハーブが、どのようなメカニズムで心身に作用しているのかを薬理学の視点で解説。アロマ関係者、医療・介護関係者、必携の書本書は,アロマテラピーやハーブ療法に携わるセラピストの方々や,これらのセラピー(療法)を日常的に使用されている方々,あるいは, これから試してみたいが,その効果と安全性にやや懐疑的な方々を読者対象にしました。
アロマの精油やハーブ類は医薬品とは異なりますが,身体に作用していることは,アロマテラピストやハーブ療法家等の方々は多くの経験と知識から得られていることでしょう。そこで今回,医薬品の作用,作用機序,治療法,毒性などを扱う基礎的学問領域である「薬理学」の概念をアロマテラピーやハーブ療法に当てはめることで,その作用のメカニズムを理解し,より高次元のトリートメント(治療)に反映してほしいと思います。そうすれば,統合医療や代替医療の分野で,より広く深い客観的かつ社会的認知を得られるでしょう。
内容は,薬理学のやさしい概説と身近な疾患別にアロマとハーブの使用の5章で構成されています。第3章の「薬の吸収,分布,代謝,排泄」は,体内に入った物質について,その入り口から出口までの過程を種々の影響要因を含めて解析する作業を解説してありますが,精油やハーブ抽出液を皮膚に適用する場合を想定した「皮膚からの吸収」についてやや詳しく述べました。第5章は,疾患ごとに原因や病態,アロマやハーブでの対処方法を示しました。医薬品としての処方が多い薬品は名称を示しましたので,アロマやハーブ療法を行う場合,その背景に薬物療法が存在しているかどうかを知ることができます。そしてどこからでも読め,必要なときに必要な部分だけ利用できるようにしました。部分的にやや専門的で難解なところもあるかもしれませんが,こだわらず,理解できる部分をつなぎ合わせても問題はありません。是非によりよい施術が提供できるよう役立ててください。
序 章 アロマ・ハーブと薬理学
第1章 アロマとハーブの薬理学
1.1 薬理学とは何か?:用語の説明
1.2 薬理学の発現メカニズム(薬はどうして効くの?)
1.3 個別作用
第2章 薬理学における測定方法
2.1 毒性試験
2.2 特殊毒性試験
2.3 抗菌性試験
2.4 抗ウイルス性試験
2.5 臨床試験
2.6 科学的・客観的効果判定の方法
第3章 薬の吸収,分布,代謝,排泄
3.1 吸収
3.2 体内分布
3.3 代謝
3.4 脂質の代謝
3.5 排泄
第4章 毒性作用のあるアロマ成分とハーブ類
4.1 精油(エッセンシャルオイル)成分の毒性作用
4.2 毒性作用の強いハーブ類
第5章 アロマとハーブの作用 各論
5.1 花粉症
5.2 うつ病
5.3 風邪,インフルエンザ
5.4 不眠症
5.5 更年期障害
5.6 気管支喘息
5.7 糖尿病
5.8 リウマチ
5.9 高血圧
5.10 細菌感染症,真菌感染症
5.11 ウイルス感染症
5.12 むくみ(浮腫)
5.13 疼痛
5.14 便秘
5.15 泌尿器系障害
5.16 肝臓障害
5.17 口腔疾患
5.18 相互作用
川口 健夫[カワグチ タケオ]
著・文・その他
目次
序章 アロマ・ハーブと薬理学
第1章 アロマとハーブの薬理学
第2章 薬理学における測定方法
第3章 薬の吸収、分布、代謝、排泄
第4章 毒性作用のあるアロマ成分とハーブ類
第5章 アロマとハーブの作用各論
著者等紹介
川口健夫[カワグチタケオ]
薬学博士。1979年北海道大学薬学部卒。米国カンザス大学、帝人生物医学研究所、城西大学薬学部を経て城西国際大学環境社会学部教授。一般社団法人ニューパブリックワークス理事、ホリスティックサイエンス学術協議会局長、NARDジャパン・アロマテラピー協会顧問、JREC日本リフレクソロジスト認定機構顧問。専門分野:癌化学療法、核酸化学、ハーブとアロマテラピー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
![無自覚な天才少女は気付かない[ばら売り] 第5話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1313481.jpg)
- 電子書籍
- 無自覚な天才少女は気付かない[ばら売り…
-
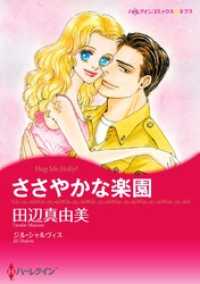
- 電子書籍
- ささやかな楽園【分冊】 11巻 ハーレ…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢、酒と理性はなじまない 1話 …
-
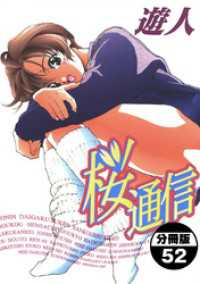
- 電子書籍
- 桜通信【分冊版】(52)
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】柳原くんはセックス依存症…




