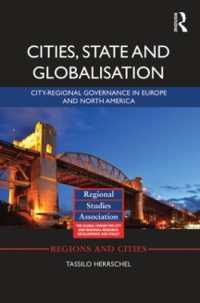内容説明
古代ギリシアの民主制の崩壊に始まり、中世を経て、ナポレオンの時代に至るまで、歴史の転換点で活躍したのは多くの傭兵たちだった。
目次
クセノフォンの遁走劇
パックス・ロマーナの終焉
騎士の時代
イタリア・ルネッサンスの華、傭兵隊長
血の輸出
ランツクネヒトの登場
果てしなく続く邪悪な戦争
ランツクネヒト崩壊の足音
国家権力の走狗となる傭兵
太陽王の傭兵たち
傭兵哀史
生き残る傭兵
著者等紹介
菊池良生[キクチヨシオ]
1948年、茨城県に生まれる。早稲田大学大学院博士課程に学ぶ。現在、明治大学教授。専攻はオーストリア文学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ずっきん
40
ヨーロッパ中世史白痴の私にとっては、入門書とはいえ中々手強いものがあった。傭兵軍事史という切り口で大まかにではあるが歴史の流れを漸く把握できた、というか目から鱗で衝撃。愛国心による戦いがフランス革命まで無く、それまでの戦いが殆ど金銭で動く傭兵によるものだったとは知らなかった。キーとなるスイス傭兵とドイツ傭兵ランツクネヒトの非道と悲哀。オランダ独立戦争からは、ん?とつい島原の乱に飛んで調べ、そこでキリシタン大名達の奴隷貿易(火薬一樽=日本人少女40人)を知る。斜めや裏から歴史を紐解くと見解が変わるなあ。2018/06/13
kawa
31
傭兵は売春婦と並ぶ世界最古の職業と言われるそうな。ウクライナでは今でもロシアが傭兵を戦場に投入している。兵制のスタンダードは徴兵による市民兵かと思っていたのだが、実は中世においては、スイスやドイツなどの次男や三男が生活のために、金で釣られて編成された傭兵制が主流ということで、時には敵対する両陣営に分かれて兄弟で殺し合いが行われる悲劇があったと言う。傭兵制度の考察を通じて中世ヨーッパ史を大掴みに把握出来る。これだけでは、まだ曖昧な理解にとどまるのだが、さらに理解を深めたいと言う意欲が引き出される。2024/09/06
スー
24
19傭兵に焦点を当て見たヨーロッパ史。有事に備え兵士を養うのは莫大なお金を消費するので必要な時だけ雇う傭兵は戦争を行う者にとって都合がよかった。しかし一転、戦争が終れば収入を失いたちまち傭兵達は盗賊となり町や村を襲う。町を破壊され生きる術を失った者達が収入を得る為に傭兵になる。そして産業が無い地域は人を傭兵として輸出する。これが有名なスイスやアイルランドの傭兵達なんですね。国軍は金がかかるので傭兵が流行る、そして統制が取れ集団戦に長けた国軍が傭兵を廃れさせ、また今度は民間軍事会社が流行り出す歴史は繰り返す2020/01/31
俊
12
傭兵の代名詞的存在であるスイス傭兵とランツクネヒトに多くのページが割かれている。創作ではかっこよく描かれがちな傭兵の実態がよくわかった。2019/02/16
のれん
11
傭兵というとなんだか無法者というイメージがあったのだが、中世どころか近世に至ってもその存在が国家に必要とされていたというのは面白い。 兵士は数を揃えることこそ要。金銭で動くというのは軍事会社も同じで貨幣主義で兵役を代替出来るようになる時点で、娼婦と同じ身体一本で稼ごうという考えは止められないのだろう。「戦いは数だよ」という某アニメの言葉がついつい出てきてしまう(笑) 一方国民主義とかの衰退については説明不足で残念。二千年というには近世中心で、概要しか説明しない傭兵も多い。次はより絞ったテーマを読みたい。2020/06/21
-
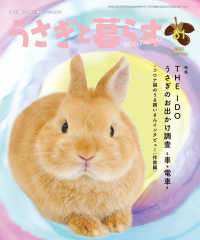
- 電子書籍
- うさぎと暮らす No.81
-

- 電子書籍
- けもの道 2016特別号 Hunter…