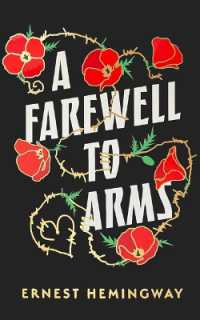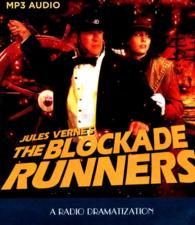内容説明
絶対平和を願う広島と、絶対悪に立ち向かう責任を問うホロコーストの違いとは何か。なぜ反戦思想が生まれ、一方で、なぜいまナショナリズムが台頭するのか。戦争を語ることの本質を、真摯に問い直す。
目次
第1章 二つの博物館―広島とホロコースト
第2章 歴史と記憶の間
第3章 正しい戦争―アメリカ社会と戦争
第4章 日本の反戦
第5章 国民の物語
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
-

- 電子書籍
- 将臣くんは、三大欲求(特にエッチ)が我…