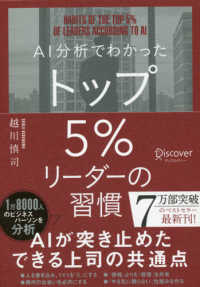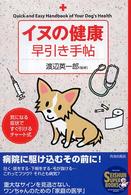出版社内容情報
【内容紹介】
礼儀正しく、子どもらしく、勉強好き。パーフェクト・チャイルド願望は何をもたらしたか。しつけの変遷から子育てを問い直す。
「パーフェクト・チャイルド」──しかしながら、大正・昭和の新中間層の教育関心を、単に童心主義・厳格主義・学歴主義の三者の相互の対立・矛盾という相でのみとらえるのは、まだ不十分である。第一に、多くの場合、彼らはそれら三者をすべて達成しようとしていた。子供たちを礼儀正しく道徳的にふるまう子供にしようとしながら、同時に、読書や遊びの領域で子供独自の世界を満喫させる。さらに、予習・復習にも注意を払って望ましい進学先に子供たちを送り込もうと努力する──。すなわち、童心主義・厳格主義・学歴主義の3つの目標をすべてわが子に実現しようとして、努力と注意を惜しまず払っていた。それは、「望ましい子供」像をあれもこれもとりこんだ、いわば「完璧な子供=パーフェクト・チャイルド」(perfect child)を作ろうとするものであった。──本書より
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
37
教育を考える人の基本書、また現実に子育てをしている親なら(直接的な効果ではないが)ふっ、と肩の力が抜ける本。そして、親とか学校を安全圏から語る奴らに、まずこれだけでも読んで出直してきやがれ、と叩きつけ(いや、表向きはそっとおだてながら)読ませてやりたい本である。実際「教育の劣化」というイメージは、逆効果かもしれぬ施策をもたらし、全ての責任を「押しつけられ」て奮闘する現実の親たちを自信喪失させる、果てしない実害をもたらしているのだから。◇宮本常一を読んで追いかけてきた近世近代の子供たち、うまく整理できそう。2015/06/16
ゆう。
32
1999年初版。とても勉強になりました。「家庭のしつけは衰退している」「しつけがなっていないから非行が増えている」など、しつけに対する印象で物事を語ってしまう傾向あります。著者は歴史的にもまた実証的にも丁寧に分析する中で、「家庭のしつけは衰退した」という論に疑問を投げかけています。階層的にみたときにどうなのか、またしつけは衰退したどころか、歴史的には家庭のなかで熱心になってきている実態などを学ぶことができました。現在は家庭でしつけをすることが社会に仕組みになったからこそ目につくのだと述べられていました。2016/07/07
りょうみや
28
大正・昭和から現代までの家庭・地域・学校の教育・しつけの役割や考え方がよくまとまっている。タイトルは逆説的で総合的に豊かになった現代ほど子供のしつけ・教育を親がコストをかけて行っている時代はないとしている。昔の農村は単に子供にコストがかけられず、またかけても見返りはなかった。地域の中で勝手に育ったが悪く言えば放置で人間関係のしがらみもきつかった。昔がよく思えるのは多くの場合思い込みだとしている。しかし、現代では教育の責任が家庭になり親子とも追い込まれやすい問題も指摘。1999年出版だが古さを感じない内容。2022/05/27
マッキー
24
「家庭の教育力は低下したか?」ということや「昔のしつけ」の内容について述べている。「昔はしつけがしっかりしていた」という言説はある方面から見ればYES、またある方面から見ればNOである。客観的なデータやアンケートに基づきながらしつけの変容を紐解く興味深い本だったと思う。 現在は経済的理由や望まぬ妊娠で余裕のない親が学校にしつけをアウトソーシングしている部分もあると思うけど、やはり行動の基盤になる部分なので学校より家庭で十分に行われるべきかと私は考える。2017/06/30
魚京童!
17
日本人を考察するにあたって、昔々のムラでの生活と工場でのマチの話がよく言われてるけど、それをごっちゃにして、今と比較していて何がしたいのかわからない。自由に生きる世の中にあってしつけもへったくれもないのだ。他人に迷惑をかけて何が悪い!そういいきったほうが楽に生きられるのだろう。迷惑をかけるのが難しくなってる。引っ越せばいいしね。迷惑をかけて、かけられる。そんな社会がなくなっている。個人で生きる。自由に生きる。縛られない生き方。脳内麻薬にラリってる。2024/12/13
-
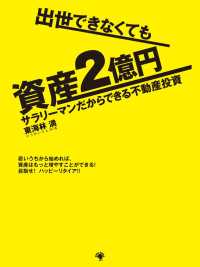
- 電子書籍
- 出世できなくても資産2億円 サラリーマ…
-
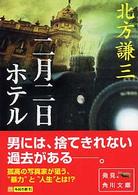
- 和書
- 二月二日ホテル 角川文庫