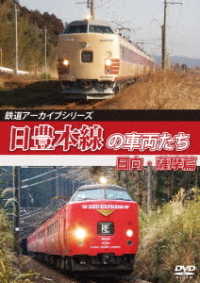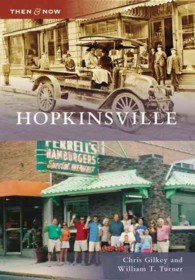内容説明
男どうしの恋の道、衆道は“武士道の華”。美少年の争奪、衆道敵討、義兄弟の契り。江戸の風俗大革命で喪われていく「性」の煌き。武士たちの愛と絆を通して日本男性史を書きかえる。
目次
第1章 忘れられた敵討
第2章 君と私
第3章 恋する男たち
第4章 義兄弟の契り
第5章 ヒゲと前髪
第6章 男振
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
匠
172
日本の多くの著名な作家が男色を経験していて驚いた。平安時代から江戸時代、明治時代の終わりまで硬派として当たり前のように認知されていた男色も大正時代には廃れていったようだが、衆道の精神性は任侠の世界などで今も息づいている。ところで、著者がハッキリ書き分けて説明していないので補足させていただくと。衆道と男色、同性愛はそれぞれ似て異なるものであって。武士や僧侶、戦士などでの主従関係・同士において深い絆を築いたのが「衆道」、男同士の性的関係を結ぶこと全般を「男色」というがこれは女性を愛せる人も含んでいる。(続く⇒2014/12/03
HANA
56
タイトルこそ「エロス」と付いているが、内容は戦国から江戸、明治前期における衆道を論じた一冊。武士道と聞くと何処か濃厚な血の漂う絵金的なエロティシズムを連想するが、斯様な男性同士の関係を中心に据えられると一層それが顕著になるなあ。念者の敵討ちから、明治のバンカラ学生の男色趣味、契りを交わした者同士の義兄弟から、江戸後期に髭と前髪が退潮したと共に男色の風潮が無くなった等と、どこを読んでも興味深い箇所ばかりであった。武田信玄や家康、信長と蘭丸が有名だけど、全体的な潮流のようなものを本書を読む事で知る事が出来た。2024/07/17
サケ太
19
衆道とはなんなのか。どのような意味があり、どのような変化を迎えたのか。男色を契機とする敵討ちの数々。強い関係性としての男色。戦国時代では戦略の男色、義兄弟の契りが危険視された理由というのが面白い。明治時代にも男色が流行していたとは……。2023/02/16
京
15
「エロス」なんてタイトルにはありますが、至って真面目な内容です(笑)武士を語る上で、実は外せない要素が「男色(衆道)」。子を生し、家を継いでいくという意味合いで一緒になる男女とは違い、精神的な繋がりを重視するという武士道においての男色。戦国や幕末など武士の闊歩する時代は勿論、それ以降の、特に大正時代まで話が及んでいるのが面白いところ。それぞれの時代で、男色(衆道)という関係にどんな意味があったのか、という部分を読むことができる一冊(・ω・*)
fseigojp
14
ややフライング気味の感がある 戦国武将と男色も合わせ読むべき2015/08/03
-

- 電子書籍
- グランドジャンプ むちゃ 2026年3…