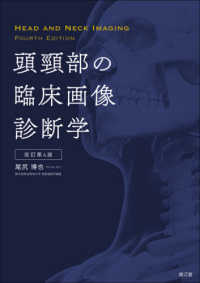内容説明
ヨーロッパ近代が生んだ遠近法と中心がたえず移動する日本特有の空間。視線の差異の発見と再発見、野性空間・田園・都市における風景観念の比較を通して、主体―客体2元論たる近代景観論の解体を論じ、ポスト・モダンの風景=〈造景の時代〉を予見する。
目次
第1章 人類学的共通基盤
第2章 視線とその変化
第3章 発見と再発見
第4章 野性の空間から自然の風景へ
第5章 田園から田園風景へ
第6章 都市から都市風景へ
第7章 風景の彼方へ―造景の時代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サイバーパンツ
12
近代からポストモダンの間、風景はどのようにして人々に認識されてきたか。西欧と日本を比較、あるいは、互いの影響を確かめ合いながら、探っていく。野生の空間はある空間が物質文明の進歩で整備されて(歴史の中で)生まれたものだとか、田舎や農村風景を一番守っているのは農民ではなく、それらを田舎らしい記号としての風景と認識している都会生活者たちというのが面白かった。2016/05/09
kaz
3
日本的感性の特徴として、「主体と客体が一体化している」ことがあげられる。一方西洋の感性としては、主観と客観をはっきり分けて考えることがある。「自分は、こう思う」というふうに。風景の見方にもそれが現れる。著者は、今後景観の問題を考えるうえで、上記のような、日本的なものと西洋的なものから「いいとこどり」することがブレイクスルーになるのではないか、と仮説を立てている(これを著者は「造景」と呼ぶ)。これはかなり説得力がある。グローバル化が叫ばれる中で、逆説的だが、日本人は日本のことをもっと知らなければならない。2017/01/08
スズツキ
3
アジアに通暁したフランス人による風景論。そこに根差す文化の比較、また日本式景観が西洋の景観法により新たに「開発」されたという考察、そして風景はそれを見る人間により如何様にも形を変えるということを実証した刺激的な論考。2016/06/21
かぺら
1
要約が難しい。ポストモダンの島宇宙的に展開される様々な主義の中から調和によって新たな様式が生まれていく様子を主体と客体を往来しながら美を追求するこれからの時代として「造景」の時代と名付け強調している。風景は「人間の世界に対する関係の、感覚で捉えられる表現」であり、各視線で見方は変わるし各視線の見方でしか見られない。近代建築以降の状況を西洋や東洋での風景観の違いなどから分析し多元的に捉え肯定しているところが風景学入門とは結論が少し異なっており、時代背景を感じられ面白かった。2019/09/07
Hiromu Yamazaki
1
主客二元論によって生じ文化というフィルターを通して解釈される「風景」だが近代の二元論に対する懐疑によりその概念が揺らいでいく。ルネサンス絵画と比較したセザンヌの技法を例として扱ったのが印象的。最終章の、記号の集合による「オリジナルを超えた本物」が、単純な悲観論に走らず新鮮。2013/10/08
-

- 電子書籍
- 被爆80年にあたっての提言---「核兵…