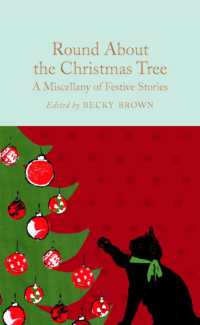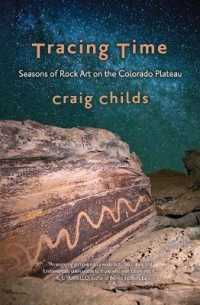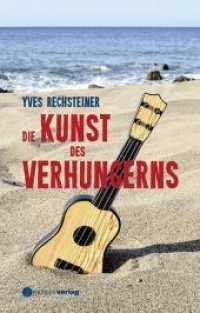内容説明
七つの海の支配者、世界の工場―大英帝国は「高度文明社会」の幕明けを告げた。観光旅行、ヴァラエティ・ショー、センセーショナルなマスコミ。消費ブームに沸く大衆社会化現象の一方で、宏大な植民地と、「二つの国民三つの階級」を内包した帝国の矛盾が、露呈し始める。
目次
1 「高度文明社会」の幕開け
2 二つの国民・三つの階級
3 版図からみた大英帝国
4 「ジャックと豆の木」と大英帝国
5 福祉国家への道―「支配の構造」改革
6 大衆社会化現象と庶民生活
7 大衆社会の舞台装置
年表
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
62
30年以上前の著作で、25年前に入手したが、豊富な図版を中心にパラ読みだった。今回通読して、これはびっくりなぐらい面白かった。なにしろヴィクトリア期でこれだけ手軽に読める社会史の本は少ないし、バランスも良い。語り口は穏やかで軽妙、でもきちんと痒いところに手が届いている。しかもナイチンゲール、『ジャックと豆の木』の裏解釈と仕掛けも多く飽きさせない。先に書いたように図版も多く、20世紀の社会保障まで届く叙述は、特に「あとがき」の(30年前の)未来予測が、今の現実をかなり言い当てていることも含め、傾聴に値する。2020/11/03
TATA
34
戦後多くの植民地を失いながらもいまだに大国の風情を漂わせる英国。確かに栄華を誇った名残として大英博物館やナショナルギャラリーは世界中を陳列しているのだろうが、翻って英国内の格差を見ればやけに矛盾を内包しているように感じる。そんな複雑なパズルを解くための一つの見方を示してくれる一冊でした。今更だけど欧州は何かと複雑だねえ。2018/04/05
kawa
32
大英帝国の最盛期は「クリミア(戦争)の天使」と呼ばれたナイチンゲールの生涯(1820年~1910年)に重なると言う。その前期は自由放任主義(レッセ・フェール)に基づく産業革命の完成形「日の没することのない帝国」が築かれ、後期は増加する余暇を活かす高度文明社会が形成され、その後期は後に「衰退100年の始まり」と評価される。明治維新の前年1867年、かの地では土曜半休制(今の若い人には何のこと?かも)が始まり、スポーツやミュージック・ホールが大流行、一方の我が国では血で血を争う革命期。比較文明論的にも面白い。2024/05/29
ジュンジュン
14
「二つの国民三つの階級」(ディズレーリ)。”世界の工場”として繁栄を謳歌した19世紀前半には、富める者と貧しき者、上流・中流・下層階級からなる社会の溝が深まった。悪しきレッセフェール(自由放任主義)の考えがそれに輪をかける。世紀の後半、ドイツやアメリカに追いつかれたイギリスは選択を迫られる。もう一度頂を目指すか、福祉国家建設(弱者救済)に向かうか。繁栄から、「衰退」ではなく成熟へ向かった社会の実相を活写する。2024/10/06
訪問者
5
何十年ぶりかの再読であるが、ナイチンゲールが生きた1820年から1910年までの英国を舞台として、いわゆるヴィクトリア朝の繁栄期の大英帝国を産業革命から福祉国家への歩みや社会生活の変化によって描き出した名著。2025/08/26