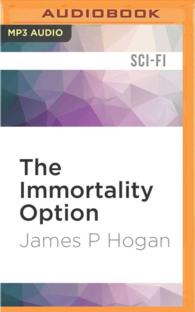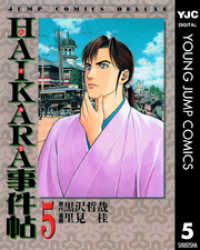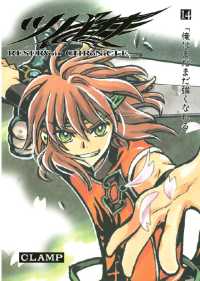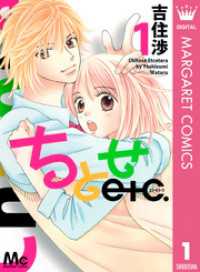出版社内容情報
【内容紹介】
かつて中央アメリカに、“太陽の国”があった。首都テノチティトランには、巨大なピラミッドや太陽の神殿が建ちならび、その人口は30万といわれた。人々は数多くの人身御供(ひとみごくう)を、神=太陽にささげ、さまざまな呪術の祭りを行なった。これがアステカ帝国である。しかし、“一の葦の年”、スペインに攻められ、一瞬にして、その文明は謎に包まれてしまった。本書は、このアステカ帝国の全体像と謎の文明を、絵文書などの資料を駆使して解明する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
19
初版は1979年とかなり古いが、アステカ文明好きなので図書館で借りました。血と死が荒れ狂う生贄という文化は現代社会に生きる僕たちから見たら凄まじい野蛮さなのだけれど(僕も血液嫌いなので実際に見たら卒倒する自信がある)、そうした行為により上位存在である神々と直接リンクし交流が出来ていた時代って考えようによっては幸せなのかもな。運命や世界のどうしようもなさを神様なら何とかしてくれるかもしれないという希望の幸せさ。そうした願いで満ちていると思えば生贄も微笑ましく……は思えねえな笑2017/08/07
fuchsia
1
結構書き込みがしてあり、どうも「金枝篇」ばりのレポートを書こうとした野望があってこの本を購入したようなのだが、全然記憶にありません(笑)多分にカソリック教義とアステカ宗教の共通点から、南米でのキリスト教伝播における教義の変容= >現地宗教化について書きたかったようです。(若い時は皆怖いもの知らずでございますな)
みんと
0
アステカ文明が好きで図書館で借りました。生け贄については、宗教上のことなのでそこまで否定的ではないのですが、この本でのあまりの凄惨さにちょっとびっくり…。2011/01/10
サアベドラ
0
約70ページに及ぶ年間の生け贄の儀式の記事は正直言って気持ち悪い。ていうかそこまで詳しく載せる必要あるのか?他のメソアメリカ文明のつながりの記述も少なく、ただアステカの生け贄習慣の生々しさだけをボコッと持ってこられた感じで、なんか消化不良。まだ詳しくわかってないのか?第1刷は1979年。すこし古すぎるかも。2006/04/22
コキア
0
古本屋の店頭でアステカというタイトルに引寄せられ即買い。 節目節目に行われる儀式が多すぎる。 大抵は心臓を取りだして太陽に捧げる。 その後は有り難く皆で戴く。 理由づけと儀式の内容が特異。 いけにえ文化、 神々に捧げる文化。 確かに、日本人にとってのハラキリも美とされてるのだから、こちらも価値のある必要なことなのだろう。2021/04/07