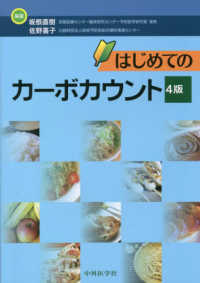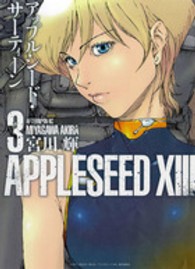- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 講談社ブルーバックス
内容説明
毒が登場する作品を題材に、アリバイ崩しや密室トリックだけでないミステリーの奥深い楽しみを引き出し、化学と自分の身を守る知識がわかるユニークな書。
目次
1 ナゼこれが“毒”?
2 身近な“物質”も使いよう…
3 猛毒はいかに使われたか?
4 “正体不明の毒”をさぐる
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
tieckP(ティークP)
11
東大の教養の学生への講義を元にしている。そのせいか、ときどき「身近な毒に気をつけよう!」的な啓発的なことが述べられていて、ややテンポを損ねている。また、われわれ文系の不遜な人間とは違い理系の学者さんだからか、律儀にネタバレを避けていて、偉いなと思いつつも、作中で毒が出てきた場面の具体的な描写や、その毒であった意義の解説などに物足りなさを覚えた。と辛口に書いたものの、類書があまりないなかで気軽にこのテーマに触れられるし、扱う作品の幅からは筆者が推理小説の大ファンなのも伝わるので、読み心地は良かった。2022/11/27
Arisaku_0225
2
アガサ・クリスティやコナン・ドイルなどの主要なミステリー文学で用いられた毒物を化学の視点で見た作品。 少し古い。2019/11/12
figaro
2
ミステリーや歴史的な事件で用いられた毒について、その特性から設定(考証)に無理がないかを検証している。最も多く取り上げられているのは砒素(亜砒酸)で、無色・無臭・無味で大昔には検出困難だったが、19世紀頃には、検出法が確立したのに、バレないと信じて用いるものがあり、「愚者の毒」といわれるようになったという件はおもしろかった。トファナ水がご婦人の武器となり、あまりに未亡人が多くなって法王庁が調査に乗り出したという話も、歴史的な興味を駆り立てた。2017/07/06
ニミッツクラス
2
知識は学習・経験だけでは身に付き難く、洞察力が重要。つまり傾向と対策、基礎と応用。啓蒙用にダイオキシン類の物性表を作っていた時、対照とした天然毒の強烈さ(185頁)に驚いた事がある。また、一般的だった接着剤や洗浄剤の有効成分が後年法律で規制され、或いはアジ化ナトリウムなどが犯罪で使用されてにわかに毒物指定されるなど、防犯や労働安全衛生では聖域無しが定着しつつある。クリスティの「蒼ざめた馬」のタリウム(215頁)はさらりと流されているが、日本でも近年類似の事件が起こった。毒殺と爆殺は極めて陰険。★★★★☆☆2012/06/01
新橋九段
1
水や二酸化炭素など身近な物質も扱ってあるので文系でも楽しめる。ミステリーと毒の歴史を見ていると人間がいかに毒殺の方法を苦心して編み出したかもわかって面白い。2013/10/25
-

- 和書
- 英文パラグラフの論理