- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
出版社内容情報
保育現場にいる発達障害のある子ども、発達が気になる子どもの行動について保育士らが困っていること、悩んでいることの声をもとに、各専門家が障害特性やよく見られる行動ごとの対応策を解説します。子どもがお友だちをたたいてしまう、じっとしていられない、人に関心がない、言葉が出ない、かんしゃくが激しい、偏食が激しいなどの行動に対して、応用行動分析学・感覚統合・TEACCHプログラム・インリアルアプローチなどの各専門家がそれぞれの発達支援のアプローチから対応などを解説し、保育をサポートします。保育士としてスキルアップしたい方に最適な1冊。
〈第1章 発達障害とは〉
「発達障害」の概念
知的障害/自閉スペクトラム症/注意欠如・多動症/限局性学習症
〈第2章 専門的なアプローチを生かす〉
障害のある子どもの支援にかかわる法律
「児童発達支援」とは
発達支援と保育をつなぐ
保育者が知っておきたい発達支援アプローチ
応用行動分析(ABA)/TEACCHプログラム/ソーシャルスキルトレーニング(SST)/感覚統合アプローチ/インリアルアプローチ
知っておきたい相談先
〈第3章 子どもとのかかわり方を探る〉
保育と医療の専門家が一緒に考える
障害児保育セミナーから分かった子どもたちの課題
CASE 1 ほかの子どもに手が出てしまう
CASE 2 集中力がなく一定時間同じことができない
CASE 3 1か所にじっとしていない/目を離すとどこかに行ってしまう
CASE 4 衝動的な行動が多い
CASE 5 ほかの子どもにあまり関心を示さない
CASE 6 ことばが出ない(出にくい)
CASE 7 理解できる単語が少ない
CASE 8 落ち着きがない
CASE 9 かんしゃくが激しい
CASE 10 好き嫌いが多い
内容説明
ほかの子に手が出てしまう、集中力がない、じっとしていられない、ほかの子に関心がない、ことばが出にくい、かんしゃくが激しいなど、こんな子どもたちに合わせた発達支援のアプローチがよくわかる!
目次
第1章 発達障害とは(「発達障害」の概念;知的障害;自閉スペクトラム症 ほか)
第2章 専門的なアプローチを生かす(障害のある子どもの支援にかかわる法律;「児童発達支援」とは;発達支援と保育をつなぐ ほか)
第3章 子どもとのかかわり方を探る(保育と医療の専門家が一緒に考える;障害児保育セミナーから分かった子どもたちの課題;ほかの子どもに手が出てしまう ほか)
著者等紹介
安藤忠[アンドウタダシ]
医学博士。大阪府立大学名誉教授。1941年北海道旭川市生まれ。鹿児島大学医学部卒後、九州大学医学部医学研究科終了。北九州市立総合療育センター所長高松鶴吉博士に師事し、発達障害児の療育にあたる
諏訪田克彦[スワダカツヒコ]
武庫川女子大学心理・社会福祉学部社会福祉学科准教授。福岡県北九州市生まれ。日本福祉大学社会福祉学部卒業後、北九州市立総合療育センターなどに勤務。医療ソーシャルワーカーの研究に取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
じゃがたろう





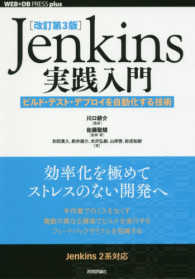
![名探偵ポワロ[完全版]Vol.21](../images/goods/ar/web/vimgdata/4907953/4907953010192.jpg)


