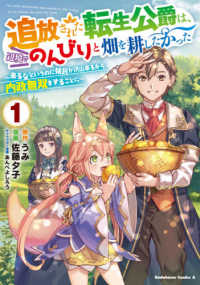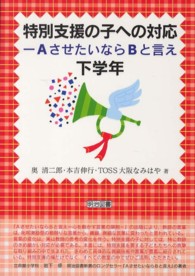出版社内容情報
「ぐうたら農法」とは、重労働となる「除草」と「耕す」作業を最小限に行う省力農法。草を活かした新発想の野菜づくりを紹介。「ぐうたら農法」とは、西村和雄先生が発案した、畑の草を活かした新発想の野菜づくり。除草はせずに耕す作業も最小限のため、ぐうたらな人でも長くラクに野菜づくりが楽しめる。定番から珍品種まで、ぐうたら農法でつくりたい42種類の野菜の育て方を掲載。
西村和雄[ニシムラカズオ]
監修
内容説明
除草不要、耕うん不要。力しごとは必要なし!永く、ゆっくり、野菜づくりを楽しめる“草生栽培”。ぐうたら流おいしい野菜の育て方42種収録。
目次
はじめに ぐうたら農法とは?
1 草を活かして野菜づくり(連作障害が出ないぐうたら農法の畑;地力の源泉は有機物と土壌生物;土が野菜を育てる ほか)
2 ぐうたら農法の始め方(旬に合わせて野菜を育てる;野菜がよろこぶ環境づくり;畝づくりの基本 ほか)
3 ぐうたら流おいしい野菜の育て方(トマト;ナス;ピーマン ほか)
おわりに これからの家庭菜園
著者等紹介
西村和雄[ニシムラカズオ]
1945年、京都市生まれ。京都大学農学部修士課程修了。専攻は、植物栄養学、植物地球化学。京都大学農学博士。同大学フィールド科学教育研究センター講師を退職後、全国で有機農業の講演・指導を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
29
先日読んだ農家の方の辛いお話で、「近所に悪いから雑草を抜く」がどれほどストレスなのか知りびっくりしましたが、そういえばアメリカでも景観重視で芝を少し刈らないでいると近所から「イメージダウンにつながるから早く刈れ」「洗濯物は干すな」とやいやい言われたっけ。焚火も怒られたなあ。ぐうたら農法のなんと魅惑的なことか。人目に使う開拓地だし、採用です。2020/09/30
さっちも
15
自然農の土づくりとは、有機物と微生物と動物をどれだけ増やして総量を大きくするか。そして、その三要素がそれぞれ作用し合い豊かに暮らす中で、狙った作物を育てる農業。ある作物にとって人間が考える必要な肥料と農薬と土いじりで丹精込めて育てたところで、自然のバランスを欠き。病害と害虫をよんでしまう。そしてそれを打ち消すために農薬を必要としてしまう。できた、過保護にブクブク育てられた野菜は立派に見えるが、根を深く張ることなく、スカスカで、本来の味を欠いている。これが本当で本来なら素晴らしいなぁ。実践してみよう2022/06/23
りるふぃー
13
一昔前の農業といえば、化学肥料や農薬などのことを勉強するイメージがあったが、最近 自然農法が当たり前のように語られはじめ、とても良いことだと思います。抜いた雑草、刈った雑草を堆肥作りに利用するには、また手間がかかってしまいますが、ぐうたら農法では、刈った雑草をそのまま雑草押さえに利用しつつ、土壌も豊かになるという。まだ実践し始めだけど、楽しみです。農業の本は、ぼかし肥料ひとつとってみてもそれぞれレシピが全然違う。正解に至る道がたくさんあって、自分のやりやすい方法を見つけていく過程がとても楽しいと思う2020/08/19
ami
5
雑草マルチで一昨年、玉ねぎを育てました。普通に🧅沢山採れました2025/02/11
くるみ
3
ぐうたら農法とは、土壌生物に土を肥沃にしてもらうため、その土壌生物に餌を与えたりしながら、野菜には少ない肥料の量で生長させること。ぐうたらとは言うものの、作物はデリケートなのでやることは多いが、他の農法よりも労力は大分削減されていそう。ホオズキの項では今は亡き祖母が作っていたなぁと思い出され、家庭菜園についていろいろ聞いておきたかったなと今更ながら思った。スーパーで売っている野菜と、自分で育てた野菜の成分は違ったりしないのかがちょっと不安。そのせいで寿命が短くなるっていうことはないのか?(心配性)2019/02/26
-
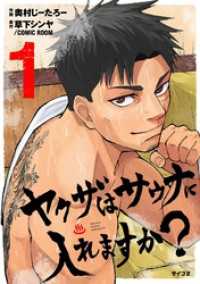
- 電子書籍
- ヤクザはサウナに入れますか?(1) サ…
-
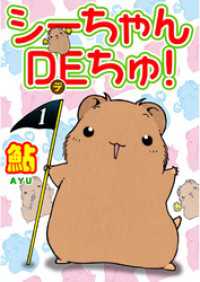
- 電子書籍
- シーちゃんDEちゅ! ペット宣言