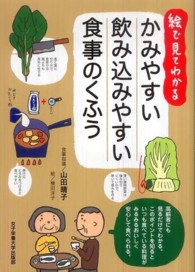出版社内容情報
「モノづくり日本」の呪縛を解き放ち、新時代のビジネス・モデルを思考する。未来を切り拓く「第3のカーブ」とはいったい何か?
「競争戦略」も「選択と集中」も「全社一丸」も限界!「モノづくり日本」の呪縛を解き、新時代のビジネスを探る。日本ビジネス再生のための思考法とは?未来を切り拓く「第3のカーブ」とは?慶大SFCの創設者井関利明と、インクス創設者山田眞次郎が語る。
【著者紹介】
慶應義塾大学名誉教授。大学改革の手本となった慶應大学SFCの創設メンバーの中心。超領域的な知の探究者。ビジネス論の革新に意欲的。「ライフスタイル」や「一人十色」といった言葉の生みの親。
目次
1章 日本ビジネスの再生をめぐる「思考法」―硬直化した通念とメガネ新調(日本ビジネスの特徴と限界;「失われた20年」の背景;新しいメディアと「メガネ新調の季節」―新しい「ビジネス認識論」の登場;ビジネス通念の落し穴)
2章 重なり合うビジネス・パラダイム―思考枠組の3つのカーブ(混迷するビジネス原理;重なり合う3枚のガラス絵;3重原理の背景;メディアの転換と3つのカーブ)
3章 一周遅れの日本の技術とビジネス―見失われた「連携・連動」の観念(技術発明の3つのカーブ;日本的技術の限界―「マクロ・テクノロジー」観念の欠如;日米における産業技術の変遷―1周遅れた日本産業;「マクロ・テクノロジー」のシャワー効果―広く深いそのインパクト)
4章 イノベーションと「創発するマーケティング」―第3カーブのビジネス・パラダイム(新しい価値創造とマーケティング;技術革新を超えたイノベーション;組織内マーケティングと「リーダー不要論」;外部組織との「業連」(Buisiness Linkage)
多数多様体のネットワーク)
5章 ビジネスの明日を創るために―新しい担い手たちそして人間回復(新しい時代を観る眼―新しい担い手たち;「再人間化」(Re‐enchantment)の動き
新しいビジネス物語の始まり―ビジネス・ロマンの再生)
著者等紹介
井関利明[イゼキトシアキ]
慶應義塾大学名誉教授、社会学博士。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学大学院社会研究科博士課程修了。米国イリノイ大学留学、慶應義塾大学産業研究所所員、同文学部教授、総合政策学部教授、同総合政策学部長、千葉商科大学政策情報学部創立とともに学部長。大学改革の手本となった慶應大学SFCの創設メンバーの中心。多くの大学の新学部創設のアドヴァイザー。専攻分野は、行動科学、科学方法論、ソーシャル・マーケティング、ライフスタイル論、政策論など
山田眞次郎[ヤマダシンジロウ]
株式会社ブレインバス代表取締役、工学博士(機械)。1990年、株式会社インクス設立、代表取締役CEOに就任。2000年、小渕恵三首相の私的諮問機関「ものづくり懇談会」のメンバー就任。2010年、株式会社ブレインバス設立、代表取締役就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Naohiko Oikawa
Kota Hiraoka
まつもとそうま
NANA
うちけん