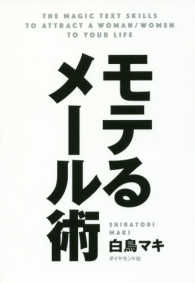出版社内容情報
日本軍の最大の敗因は「いかに金属で優れた兵器を効率的にたくさん作るかという根本的な戦争の手段が未熟だったことにあった。
仮に当時の日本に資源が潤沢にあったとしても、やはり太平洋戦争には負けているだろう。それは「いかに金属を戦力化するか」、つまり「金属で優れた兵器を効率的にたくさん作る」という根本的な戦争の手段において、日本は太刀打ちできなかったからである。
【著者紹介】
中大法学部卒。国士舘大政治学研究科修士課程終了。著書に小社『日本軍の敗因』、『なぜ日本陸海軍は共同して戦えなかったのか』(光人社)『陸海軍戦史に学ぶ負ける組織と日本人』(集英社新書)などがある。
内容説明
なぜ日本は優秀な兵器を造れなかったのか?兵器生産の本質をついた今までにない渾身の書!
目次
第1章 戦争のタンパク質「銅」
第2章 戦争の骨格となる「鋼」
第3章 ベースメタルに加わった軽金属
第4章 金属工業のビタミン「レアメタル」
第5章 国産兵器が抱えた問題点
第6章 失敗した総力戦体制の構築
著者等紹介
藤井非三四[フジイヒサシ]
1950年生、神奈川県出身。中央大学法学部卒、国士舘大学政治学研究科修士課程修了。朝鮮戦争史専攻。(財)斯文会、出版社勤務の後、編集プロダクション「FEP」を設立、主に軍事関連書籍の企画、出版に当たる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
33
母から譲り受けた裁縫バサミにはSweden Steelという刻印がある。研ぎ直したら恐ろしいほど良く切れる。戦後10年ぐらいは刃物用の鋼もまだ十分に生産できず、輸入していたというわが国の産業史の証人だ。第二次世界大戦中、クルップ社の技術を元にスウェーデンのボフォース社が高性能の機関砲を製造。わが国は英軍から鹵獲して、コピーしたが、すぐに断念。なぜなら、高品質なスウェーデン鋼を入手する当てがなかったからだ。火山国のわが国で産出される全ての鉱物には硫黄や燐が混ざる。それが、兵器の性能の差、戦力の差となった。2014/10/20
coolflat
14
資源を求め、朝鮮、満州、最終的には太平洋戦争へと日本は突入したが、資源を手に入れる事だけが目的化し、「資源」=「金属」の扱い方(採掘→選鉱→輸送→製錬→加工というシステム)にまで頭が回らなかったというのが、日本の敗因だ。笑うのは、資源を求めたはずの朝鮮、満州にそれほどの資源がなかった事。小銃を統一せず、異なる口径の小銃を使っていた事。現場は混乱し、短期的に大量生産する事もままならなかった。それに比べ列強は単純さを追求し、信頼できる実包、大量生産のラインが整備されている弾薬を使い続けた。そりゃ日本は勝てない2016/03/23
ようはん
7
ニッケルやタングステンといったレアメタルや銅や鉄鋼等の金属の確保という視点での太平洋戦争。国内はもとより植民地や占領地で充分な金属を確保する術を持たず、陸軍海軍の対立による物資の奪い合い等結局当時の大日本帝国という国が世界大戦を生き抜くのには体力不足だったという感。2019/10/27
氷雨@exice
7
弾薬ねぇ!銅がねぇ!鉛もそれほど足りてねぇ! 亜鉛もねぇ!アルミもねぇ!満州取っても何もねぇ! 石油がねぇ!補給もねぇ!タンカーつくる鋼材ねぇ! ニッケルねぇ!コバルトねぇ!人造石油もつくれねぇ! 陸軍と!海軍が!希少資源の奪い合い! 南方資源はあるけれど!技術者戦地でぐーるぐる! 2013/10/26
dongame6
6
金属資源という側面から太平洋戦争(というか日本軍)を見た本。レアメタルとタイトルにあるが、ベースメタルについての記述も多い。鉄、銅、アルミなど各資源がどういった特性でどういう用途に使われているか等が具体的なエピソードと共に書かれており基礎知識がなくても分かりやすい。また各金属の産出元や精製、加工など産業面についても書かれており大変興味深かった。資源が偏在する地球でどういった戦略を取って軍需産業を回していくかという戦略観も必要という事が良く分かる。ただ本の後半はタイトルのテーマから脱線気味で残念。2013/10/28