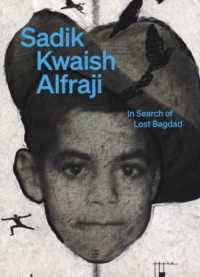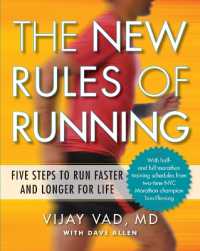内容説明
「子どものために」という親心が子どもを追い詰めている?子どもの個性は、「できること」にしか認められず、「できたか、できなかったか」の成果主義評価の下で悩む現代の子どもたち。厳しい現実を生き抜くために、今本当に必要な力とは?38年間小学校の現場で子どもたちとトコトン向き合い、「いのちの授業」で数々の教育賞を受賞した著者が語る、親子の未来を切り拓くメッセージ。
目次
第1章 「子どものために」正しいこと、正しくないこと(「できる・できない」ではなく、豊かな人間関係に目を向ける;心の「溜め」を育もう;変わる、社会。 ほか)
第2章 子どもを信じて受け止めるには(子どもは「いじくり」で育つ;農業、自然とかかわり合う;命の教育。死の教育 ほか)
第3章 今日から「子どものために」できること(子どもと大人は違うことを忘れていないか?;大人が自分を語り込もう;キャッチャーとピッチャー ほか)
著者等紹介
金森俊朗[カナモリトシロウ]
北陸学院大学人間総合学部幼児児童教育学科教授。同大学地域教育開発センター長、上越教育大学・金沢大学非常勤講師。1946年、石川県能登生まれ。金沢大学教育学部卒業後、石川県内の8つの小学校で教諭を勤め、定年退職後、現職。80年代より「仲間とつながりハッピーになる」という教育思想をかかげ、人と自然の繋がりを模索しながら様々な教育を実践。1989年に妊婦を招いて行った性の授業を皮切りに本格的にいのちの授業を開始、1990年には末期がん患者を招いた「デス・エデュケーション」を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mana
蘇我クラフト
つかじーにょ
はたけ
Honesty