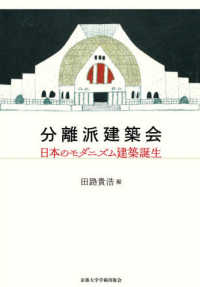- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 浮世絵・絵巻・日本画
出版社内容情報
江戸時代の中頃、西洋画の遠近技法を取り入れた「眼鏡絵・浮絵」が生まれた。その中に幕末・明治期にかけて泥絵の具で描かれた大名屋敷の「泥絵」が数多くあった。江戸土産として人気があったが、その後埋没していたコレクションを発掘紹介する。
内容説明
泥絵―泥絵の具を使い遠近法によって描かれた肉筆画。幕末に江戸みやげとして評判を呼んだ泥絵を収録。渡辺紳一郎コレクションを中心に初めて本格的に紹介。今甦る幕末の大名屋敷。
目次
泥絵編(西の丸大手前;日本橋;大手前姫路藩酒井家上屋敷;霞ケ関広島藩浅野家上屋敷・福岡藩黒田家上屋敷;霞ケ関登城広島藩浅野家上屋敷・福岡藩黒田家上屋敷 ほか)
概説編(埋もれていた泥絵;江戸の大名屋敷)
著者等紹介
平井聖[ヒライキヨシ]
東京工業大学教授を経て、現在昭和女子大学学長・福井県立博物館館長・東京工業大学名誉教授。工学博士
浅野伸子[アサノノブコ]
現在昭和女子大学国際文化研究所客員研究員・同大学非常勤講師。学術博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
misui
4
泥絵具という舞台装置の背景などに用いる安い絵の具で描かれ、100%遠近法を意識しているのが「泥絵」とのこと。空と道路の空間を大きく取り、遠近法は誇張され、人物が描かれているにしても画一的な表現。泥絵具ののっぺりとした色合いとグラデーションで、画面には不思議と静謐な空気が漂っている。なんとなくキリコが江戸の風景を描いたらこうなるのではと思わせる。解説は描かれている大名屋敷や町並みについての言及が主で表現にはあまり踏み込んでいない。そんなに注目されてないジャンルなのかな。2014/09/27
takao
1
ふむ2023/07/13
-

- 和書
- 都市への権利 筑摩叢書