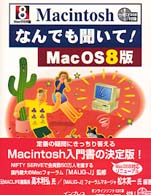内容説明
問題は、レアメタルではない!「産業の血管」である銅さえも、あきらかに生産のピークを迎えた。あらゆるメタルを爆食し世界中の鉱山を買い占める中国と、超大型合併で寡占が進む資源メジャーが死闘を繰り広げるなか、日本はどのようにして「ものづくり」を続ければいいのか?新しい資源ナショナリズムと資源獲得競争を生き抜く道を探る。
目次
序論 多金属時代
第1章 国際メタル資源メジャー
第2章 新たな資源ナショナリズム
第3章 ピーク・メタル
第4章 中国のメタル獲得戦略
第5章 「ものづくり立国」日本の未来
著者等紹介
谷口正次[タニグチマサツグ]
1938年生まれ。資源・環境ジャーナリスト。九州工業大学鉱山工学科卒業。小野田セメント、秩父小野田、太平洋セメント各社で役員を歴任し、鉱物資源事業、環境事業等を手がける。現在は、執筆・講演活動を中心に、鉱物資源と環境の未来について提言を続ける。国連大学ゼロエミッションフォーラム、サステナビリティ日本フォーラム、モノづくり生命文明機構の各理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Humbaba
7
資源は有限である.そして,そう簡単には増産することは出来ない.需要が増えれば,その分だけ供給側の力は強くなる.しっかりとした国家戦略を持たないと,非常に不利な条件でしか輸入できなくなってしまう.2013/03/04
Humbaba
5
工業製品は需給に応じて生産量を調整可能である。しかし、その元となる金属資源は必ずしも需給に対応できるわけではない。また、大量生産を行おうとしても価格が下がるどころか寧ろ高騰する可能性も高い。高価でも手に入るならまだましであり、物によってはそもそも手に入らなくなる危険もある。2016/05/13
アイス1億円
5
エアコンの取り付け工事でうちにきた業者の方が、エアコンの室外機には銅が何キロか使われていて、持っていくところに持っていけば今の銅の相場でいうと五千円?(うろおぼえ)くらいになりますよ、とおっしゃっていた。本当はいけないことらしいけど。日本がもし潤沢な天然資源を手に入れたとしても、アメリカにもっていかれそうな気がします。2015/06/19
BATTARIA
1
前半では、世界各地での鉱山をめぐる環境破壊と、それによる地域住民とのトラブルなどについて、様々な事例を挙げている。 大量のテーリング(採掘の際に出た鉱滓)の垂れ流しとは言語道断ながら、同類の事例を繰り返されても興ざめ。 これじゃ鉱石の採掘自体が悪事だと言ってるみたいで、身もふたもない。 日本の資源外交のお粗末さ、ひいては資源に関する教養のなさを嘆いているが、それに著者の関する提案は、ためにする議論にしか思えない。 そして何よりも、本題であるはずの銅に関する記述が少な過ぎてガッカリ。2011/04/20
slash
0
日本の資源外交の遅れが取り返しのつかないことにならないように祈ります。2009/01/10
-

- 洋書電子書籍
- Growth and Applicat…
-
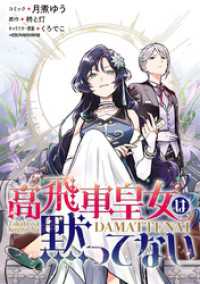
- 電子書籍
- 高飛車皇女は黙ってない 【連載版】: …
-

- 電子書籍
- 超人ロック 完全版 (24)シャトレーズ
-
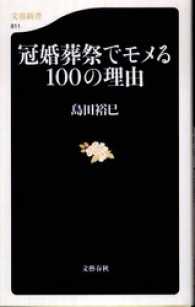
- 電子書籍
- 冠婚葬祭でモメる100の理由 文春新書