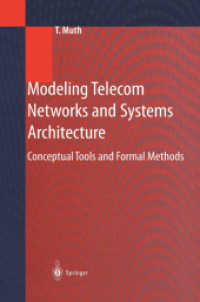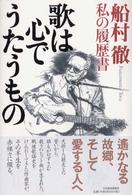- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
出版社内容情報
旧知の仲の3人が武装解除し、居場所について語り合った胸の内生きる意味を見失いそうになりそうな成熟社会の中で、自分の居場所をきちんと確保することの大切さが問われている。そこで、精神科医として大阪で精神科緊急救急病棟の設立・責任者を務めた後、今や東京を中心にテレビなどメディアでも活躍している名越康文氏、東京都大田区で生まれ育ち東大を出ながら、神戸女学院大学教授として長年神戸で暮らし、退職後も神戸に道場を開いて思想家・武道家として異彩を放っている内田樹氏、そして内田氏と小中学校が同じで、東京で多くの会社の経営にかかわりながら、現在は東京の私鉄沿線に開いた自分の喫茶店にいるのがいちばん居心地がいいと話す平川克美氏。旧知の仲の3人が、三者三様の生き様を通して、居場所とは何か、自分らしさやつながりとは何かについて、胸襟を開いて語り合う。心が温まり、思わず笑いがこみあげる話の中に、叡智が散りばめられた1冊。
はじめに「偶然の喫茶店主」(平川克美)
第1章 いちばん自分らしい場所
第2章 つながるということの本質
中締め「居場所という聖域」(名越康文)
第3章 好き嫌いと価値観の共有
第4章 師匠の存在、家族が自己にもたらすもの
おわりに「人通りの多い書斎」(内田樹)
内田 樹[ウチダ タツル]
平川 克美[ヒラカワ カツミ]
名越 康文[ナコシ ヤスフミ]
内容説明
自分の居場所を見つけられない人が増えていると言われる時代、それぞれ違う立場で活躍してきた内田樹・平川克美・名越康文の朋友の3人が、自分らしさとは、つながりとは何かについて鼎談。昔話に花が咲いたと思ったら、話は思わぬ方向に…。叡智が詰まった言葉の数々にハッとさせられる1冊。
目次
第1章 いちばん自分らしい場所(自分が落ち着ける場所;居心地のよさとは ほか)
第2章 つながるということの本質(小学校時代の指定席はいちばん前;あやふやな決闘の記憶 ほか)
第3章 好き嫌いと価値観の共有(嫌韓と在特会;経済成長と隣国感情 ほか)
第4章 師匠の存在、家族が自己にもたらすもの(憧れの人について;自己評価と対価 ほか)
著者等紹介
内田樹[ウチダタツル]
1950年、東京都大田区生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院博士課程中退。神戸女学院大学文学部総合文化学科を2011年3月に退職。現在、同大学名誉教授。専門はフランス現代思想、武道論、教育論、映画論など。07年、『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)で第6回小林秀雄賞を受賞。『日本辺境論』(新潮新書)で「新書大賞2010」を受賞。11年、第3回伊丹十三賞を受賞
平川克美[ヒラカワカツミ]
1950年、東京都大田区生まれ。75年、早稲田大学理工学部機械工学科卒業。77年、翻訳を主業務とする株式会社アーバン・トランスレーション設立、代表取締役となる。99年、シリコンバレーのインキュベーションカンパニーであるBusiness Cafe,Inc.設立に参加。2001年、株式会社リナックスカフェ設立。声と語りのダウンロードサイト「ラジオデイズ」を運営する。現在、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授も務める
名越康文[ナコシヤスフミ]
1960年、奈良県生まれ。精神科医。相愛大学、高山野大学客員教授。専門は思春期精神医学、精神療法。近畿大学医学部卒業後、大阪府立中宮病院(現:大阪府立精神医療センター)にて、精神科救急病棟の設立、責任者を経て、99年に同病院を退職。引き続き臨床に携わる一方で、テレビ・ラジオでコメンテーター、映画評論、漫画分析などさまざまな分野で活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
おさむ
Nobuko Hashimoto
ノクターン
*
-
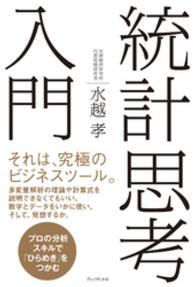
- 電子書籍
- 統計思考入門 - プロの分析スキルで「…
-

- 和書
- 長野県民の100年史