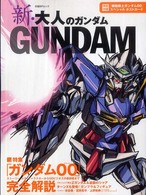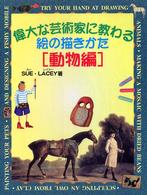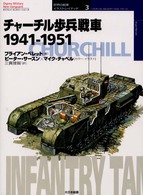- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
開成高校の授業で使われていた『武士道』を読み解く独自テキスト。
目次
第1篇 新渡戸稲造と『武士道』
第2篇 『武士道』に学ぶ心(道徳体系としての武士道;武士道の淵源;義;勇―勇敢と忍耐の精神;仁―惻隠の心;礼;誠;名誉;忠義;武士の教育と訓練;克己;切腹と仇討の制度;刀―武士の魂;女性の教育と地位;武士道の影響;武士道はなお生き残れるか;武士道の将来)
第3篇 『武士道』からのメッセージ
著者等紹介
大森惠子[オオモリケイコ]
1951年4月8日生まれ。日本女子大学文学部英文学科卒業後、同大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了。同大学附属中高英語科非常勤講師、法政大学エクステンションカレッジ講師等を経て、現在は東京国際大学言語コミュニケーション学部非常勤講師。日本英文学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
29
十五歳で成年に達し、独立した行動を許されると、武士はいかなることにも充分役に立つ鋭利な武器を所有することに誇りを感じることができた。この危険な武器を所有することによって、彼は自らを尊び、責任を果たすという感情や態度を身に着けた。「刀は伊達に差さない」彼が腰に差しているものは、彼がその心の中に抱いているもの、忠義と名誉の象徴である。二本の刀、長いものと短いもの、それぞれ「大刀」と「小刀」、または「刀」と「脇差」は決して彼の脇腹から離れることはない。家では、書斎や客間のもっとも目立つ場所に飾られるのだ。2019/12/12
てんちゃん
2
何のために生きるべきか、人間としての存在価値に関する問い。これはいつの時代も、洋の東西を問わず、語られる悩み。色々な考え・価値観に出会う度に、それらに目が泳ぎがちになるが、その中でも確固とした自分を持つとに対する自信を与えてくれるのが武士道なのだろうか。「不死鳥は己れ自身の灰の中からだけ蘇るのであって、決して渡り鳥ではなく、また他の鳥から借りた翼で飛ぶのではないことを忘れてはならない。」自分を肯定し、信じて生きることで、他も受け入れられるのではないか。2019/10/27
きたてる
1
「宗教教育がなくて、それでどうして道徳教育ができるのですか」我が国の精神文化を様々な角度から諸外国の人にもわかりやすいように説明されている「武士道」。現代の若者には「武士道」という表題、言葉だけでなかなか受け入れづらいものかもしれない。更に解説を加えることによりわかりやすくなっている。若者だけではなく我々も今一度見直す機会となるであろう。 2017/10/28
風見じじい
1
封建時代の家臣の不文律である武士道とキリスト教を対比して、外面的規範としての武士道に対しキリスト教は内面の規範であると言っている。敗戦で、武士道的な規範も消えてしまうのはやむをえないと思うが、ノブレスオブリージュも同時に消えて自己の利益しか考えない人が増えてしまったと思う。新渡戸の訳文を太字で書いてあるが、解説文と一体になって本文と解説の違いが意識させない点はマイナスかと思う。小さい点だが、「蜻蛉つり今日はどこまで行ったやら」は千代女の作と言っているが異説もあり気になりました。2015/03/10
Yuta
1
僕はアメリカのキリスト教の高校に1年間通ったことがあり毎日バイブルを読む時間には武士道を片手に相対的にまさに新渡戸稲造を模範として自分の人生の指針・思想をどう築くべきか考た。人は人生の指針、思想、理想がなければ生きていけない弱い生き物。やはり素晴らしい本でこの本を元に武士道を読み直したい。道徳とは方向性を見失った時に必要なもの、人類の普遍的な道徳とは何か儒教とキリスト教を融合させ武士道を完成させた新渡戸という先駆者が明治にはいた。現代の日本も同じではないか。日本人として若者として読むべき重要な本。2014/12/29