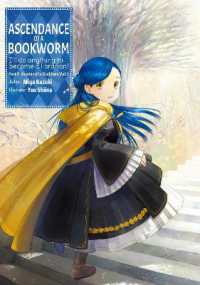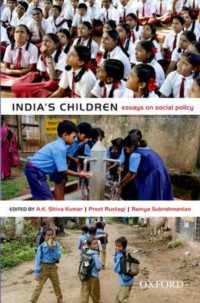- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
「脳トレ」の常識はウソだらけ!そんなに右脳だけ鍛えて大丈夫?その効果の限界をデータから導く。
目次
第1章 脳の活性化とは何か?(画像診断装置が示すもの;脳の活性化=脳機能のアップではない;高齢者の脳の機能は画像で調べられるか)
第2章 能力開発で本当に脳機能は向上するのか(脳を調べて人の考えがわかるのか;3歳までの教育で人の能力は決まらない;右脳のトレーニングは試験や処世の成功を保証しない)
第3章 間違った脳トレは人を幸せにしない(記憶のトレーニングはどのように役立つか;考えすぎは不眠のもとである;脳トレは老いの摂理に反している)
第4章 本当の脳トレは毎日の生活のなかにある(ミラー細胞の活用で脳力を高める;言葉がもたらす「プラシーボ効果」を利用する;脳を鍛えるための三つの習慣)
著者等紹介
高田明和[タカダアキカズ]
1935年、静岡県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業、同大学院修了。アメリカ・ロズエルパーク記念研究所研究員、ニューヨーク州立大学大学院助教授、浜松医科大学教授を経て、同大学名誉教授。医学博士。専攻は生理学。日本生理学会会員、日本血液学会功労会員。最近では永年実践している禅についての著書も多く、注目を集めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カフ
3
TVでも最近話題の脳トレの問題点について。MRIで見る画像、血流量の増加が脳の機能を向上させている絶対的証拠にはならない。 忘れることは悪ではない。年をとり忘れることで健康的な精神を維持していると言えるのだ。脳も体の一部なのだ。適度な運動、適切な生活リズム、興味を持ち楽しみながら考える。そんな些細と思われる健康で文化的な生活が一番の「脳トレ」である、と筆者は語る。2011/03/10
最終バック九番手
3
いつまでも覚えておくよりもずっと忘れたままにしておいた方がいい事のほうが圧倒的に多いんだから脳トレを安易に始めてはいけないというお話…「ゆっくり呼吸」と「腹筋トレーニング」の併用のほうがゲームや脳トレ本なんかよりよっぽど効果的でしかもタダでできる…初版発行:2009年6月10日…本体705円2009/10/18
gasparl
2
禅の観点をベースに昨今持て囃されている脳トレに疑問を投げかける本です。巷で言う能力開発/右脳開発が鬱や不眠を招いている等の事例も紹介し、脳トレはゆっくりとした呼吸法、腹筋の鍛錬、あとは習い事程度で十分とのこと。古くから言われている健康法で、本来の脳開発は十分なのかもしれません。2010/03/14
ととむ
1
まあ100マス計算とかいい年こいた大人がやるもんじゃないわなあ。やって脳の特定部位の血流がふえたら何なの、という話。短絡的な結論に飛びつくのは思考の横着だわな。2014/09/07
M_Study
0
脳トレでよく目にする脳のfMRI画像などは、脳の血流あるいはブドウ糖消費が増えていることを示すだけで、実際に脳が活動したことを示すわけではない。忘れることも大切な能力。歳をとるほど、思い出すのは嫌なことが多くなる。安易に脳トレすると、嫌なことも忘れられなくなる。ストレスは脳に対する一番のダメージ。脳の衰えを防ぐには、ストレス対処が重要。2016/04/07