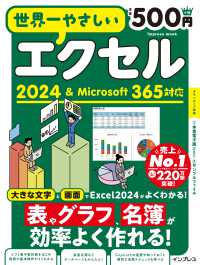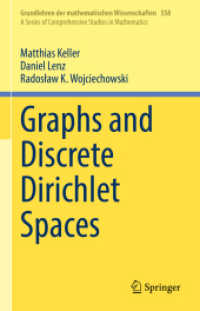- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
学校では教えられなかったイマドキの表記法が蔓延する理由は?『ありえない日本語』の著者が実例を元にデジタル時代の日本語表記の可能性を探る。
目次
第1部 導入編 ヴィジュアルな日本語(日本語はヴィジュアル重視;デジタル書きことば革命とその後)
第2部 実践編 ネオかなづかい(現代かなづかいからネオかなづかいへ;ネオ小書き文字「っ」;ネオかな小文字;ネオ外来語表記;ネオ四つがな;ネオ濁点文字;ネオ長音符号;ネオ句読点)
著者等紹介
秋月高太郎[アキズキコウタロウ]
1963年東京に生まれる。東北大学大学院情報科学研究科博士課程後期修了。博士(情報科学)。現在、尚絅学院大学総合人間科学部表現文化学科准教授。専門は、言語学。ことばとその話し手が属する文化・社会とのかかわりや、話し手がことばを用いるときに生じる効果について研究している。特に、日本の若い世代のことばと、マンガ、アニメ、J‐popなどのサブカルチャーとのかかわりに関心をもっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gorgeanalogue
4
音韻論が苦手な私にとっては、退屈な部分もあったが、後半、ネオ四つがな、ネオ濁点文字などの章は日本語表記史の入門にもなっていて、面白く読めた。ただし、事例を踏まえて提案される「ネオかなづかい」はどれも説得力がない。どうしても「規範」への志向がうかがえるからか。あとがきで書かれる「ことばのレイアウト」という視点とその「効果」(それが「ビジュアル」であるわけだが)を一貫して強調したほうが説得力があったと思う。2019/09/25
ブルーローズ
1
言語学の専門家による本。書き言葉の現状を認識し、いっそこうしちゃえ、という提案も盛り込んでいる。明治の「美文調」や「翻訳調」を意識しているのかも。2010/01/24
sfこと古谷俊一
1
ネオかなづかい、と称して、現代日本のケータイやネットなども含めた文字の書き方を肯定的に考えるという、じつに目の付け所がいい本。新書とはいえ、歴史的経緯の調査などが甘く感じたとこがあって、第一章は残念であった。提案自体は面白いのでもったいない。たたき台として考えるといいかな。2009/01/25
大王岡
0
促音や拗音はなるべく小書きにする。と、必ず小さく書かなくても良いというのと、外来語の表記が細かく決まつているのは知らなかつた。決まる前、江戸時代や室町時代などの昔の表記が見れて面白かつた。2012/05/21
はにゃん
0
☆☆サブカル好きな言語学者による、ネオかなづかい論。ネットやメールに見られる、おかしな表記について語られている。すっかり昭和なはにゃんは、元々あまり得意じゃないし〜と思っていたが、いくつも該当する表記を使っていた。orz2010/06/20
-
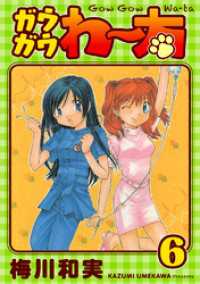
- 電子書籍
- ガウガウわー太 完全版 6巻