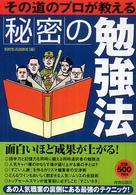- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
これからは、危険や災害を見通し、備える力・いざというとき瞬時に判断する力・人と人とをつないで協力する力・困難の中でなけなしの条件を引き出す力が必須である。それらの力=真の学力を習得、発揮するための具体的なプロセスを開示した現代人の生きる教科書。
目次
第1章 国家は子どもに何を求めているのか
第2章 教師の指導力不足は本当か
第3章 子どもの生活と内面世界はどうなっているか
第4章 いじめをどのように克服するのか
第5章 本物の学力とはなにか
第6章 親は子の成長とどう向きあうか
第7章 生き抜くための土台づくり
著者等紹介
金森俊朗[カナモリトシロウ]
1946年石川県能登生まれ。金沢大学教育学部卒業。小学校の教師となり、2007年まで8校で、教鞭をとる。80年代から本格的に性と死の授業に取り組み、日本で初めて、小学校でデス・エデュケーションを実践する。情操教育の最高峰として、全国から注目を集める。97年、中日教育賞を受賞。2003年に放送された金森学級の一年間を記録した番組、NHKスペシャル「涙と笑いのハッピークラス」は、大きな感動を呼び、アジアで初めて、バンフ国際テレビ祭グランプリ、日本賞グランプリを受賞した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ryuya Matsumoto
5
子供たちにとって学校はどんな場所であるか。自分自身の子供たちへのまなざしはどうだったか。いろいろとあらためて考えました。今の学校は「セレモニー」ばかりで「フェスティバル」がない。その通りだと思います。反省。明日は、どんな楽しいことをしようかなと、前向きな気持ちになりました。2015/12/06
eco
2
そこまで印象に残るフレーズや考え方はなかった。2024/02/25
Sugaya Masaki
2
極論乃至は反常識的であるが、社会から見れば学校とはあってもなくてもかまわない存在である(と思っている)。それは学校(中・高)で学ぶことの95%は社会に出て必要ないからだ。氏の述べる学力こそ真に子どもたちが身に付けるべきもので、社会に出てから求められる力である。国語の授業においては自分の授業を受けた子どもが社会に出てから活躍できるだけの言語能力(=仕事を円滑に進めるための諸能力)を身に付けさせてやれたかが授業評価の軸になる。2017/10/15
Don
2
・学校は人と人とが激しくぶつかり合って,失敗を繰り返しながら,失敗が当然の権利として認められなければならない社会である。 →自分をしっかりと顧みたい文。子供に対して不寛容になっていないだろうか。 大切なことはハードルを下げることでなく,ハードルに挑戦する気持ちを育てること。 学校の活動を「日常⇔非日常」「セレモニー的⇔フェスティバル的」の2軸で考えてみようと思った。近年の風潮はフェスティバル的な要素を排除する傾向はないだろうか。日常の中で充足感を得られにくい子の活躍の場を提供できているだろうか。 2013/08/25
はたけ
1
以前読んだ『「子どものために」は正しいのか』よりも理論的内容でした。ほかの本では理解しにくかった通常の授業についての考えや、イジメ問題の解決方など盛りだくさんでした。心に残っているのは「教師はキャッチャーであれ」という言葉です。また「自分イジメ」という考え方。たしかに現代は自分イジメをしやすく、そんな環境なら他者イジメをしちゃうなぁと思いました。私の学校に他者イジメがなかったのは、きっと自己肯定感が強かったからなのでしょう。子どもまるごと認められる、そんな教師になりたいものです。2017/05/27