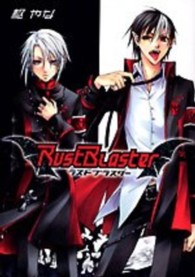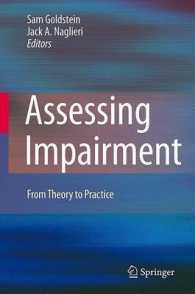内容説明
モノづくりは感性に頼らない!「ハウルの動く城」「もののけ姫」サントリー「伊右衛門」CM…あの名曲はここから生まれた。時代の風を読むために必要な「感性の正体」を探る。
目次
第1章 「感性」と向き合う
第2章 直感力を磨く
第3章 映像と音楽の共存
第4章 音楽の不思議
第5章 日本人とクリエイティビティ
第6章 時代の風を読む
著者等紹介
久石譲[ヒサイシジョウ]
1950年、長野県生まれ。国立音楽大学作曲科卒業。現代音楽の分野より出発し、82年にファーストアルバム「INFORMATION」を発表、ジャンルにとらわれない独自のスタイルを築き上げる。84年に宮崎駿監督のアニメ「風の谷のナウシカ」の音楽を担当し、多くの感動を呼ぶ。以降、宮崎駿監督の「となりのトトロ」「もののけ姫」や北野武監督の「HANA‐BI」「菊次郎の夏」など多くのヒット作の映画音楽を担当し、名実ともに日本映画音楽の第一人者となる。98年に長野パラリンピックの総合演出を務めたほか、2001年には「Quartetカルテット」で映画監督としてもデビュー。近年は中国、韓国の映画音楽を数多く手掛け、05年には「トンマッコルへようこそ」で日本人として初めて韓国の映画賞(大韓民国映画大賞最優秀音楽賞)を受賞するなど、今後も世界的な活躍が期待されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
34
ステイホーム書庫整理中。夫がついに二階の押し入れ半分を占める蔵書整理に着手!出るわ出るわ本人もあきれているのだが、出てきた本が面白いくらい彼らしくて楽しい(タイトル買いするくせがあるようなのがおかしい)。この本もタイトル買いしたんだろうなあ。久石さん=ジブリですが、この人の文章は初めて読みました。…もっと早く読めばよかった!ずばりといいたいことが簡潔にまとめられ、とにかく作りたい、な気持ちが伝わってくる。作業中に読みふけってしかられました。2020/05/15
ホークス
30
音楽家久石譲氏の、経験も栄光も相対化する囚われない姿勢に打たれた。作曲の難しさとポイントを素人にイメージし易く説明する見識にまず驚く。圧巻は映画音楽論で、映像と音楽の相乗効果が作品をレベルアップする原理が述べられる。一方で北野武、宮崎駿など監督によって、また国によって映画と音楽に対する考え方は大きく違う。状況外音楽(所謂映画音楽)と状況内音楽(物語の世界の音)の話も面白い。日本人のオリジナリティの弱さは、私見では空気文化が強力過ぎて、相対化する力が弱いためだと思う。この物言いすら異端視されかねない。2017/10/14
booklight
24
プロの作曲家。その考え方や日常生活を学べる。プロとは、オーダーがあってそれにこたえること。だからコピーライターやデザイナーと同じ。つまり作曲家の仕事術。ただ、そこには根源的な何かに立ち向かっているわけではない。それはたとえば芸術家の仕事なんだろう。それでも創造性を仕事にして、予定調和が嫌われる世界で、いかにオーダーにこたえていくか。ロジカルなものを95%まで積み重ねて5%の創造を加える。オーダーにも答えつつ自分の作品も作っていく。ピアノも演奏する。自分の領域を広げていく姿がすごい。summer、大好きです2024/11/23
糜竺(びじく)
22
宮崎駿さんの映画のサントラなど数多くの作品を生み出している、大好きな作曲家の久石譲さんの頭の中身を少し垣間見えた気がする。2021/10/10
akira
22
新書。 大学の頃独学で練習したのが、久石さんの曲だった。一回聴いただけで胸に残るメロディ。それは、どのように生み出されているのか。作曲の裏話や、宮崎監督とのエピソードなど。魅力ある一冊。 仕事論。音楽論。心の持ち方など。レベルはまるで違うが、どんな人にも通じる何かがある。10年以上前から言われていたAsiaというテーマ。久石さんの目に映るものは。 自身の中にある臨界点を超える。かつて、ドキュメンタリーでも言われていた。そうしたとき、人の心を動かすものができる。 「飛び越えた、といえる瞬間がやってくる」2015/01/27
-

- 電子書籍
- ジパングを探して!
-
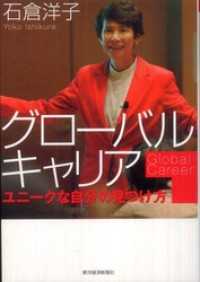
- 電子書籍
- グローバルキャリア ユニークな自分の見…