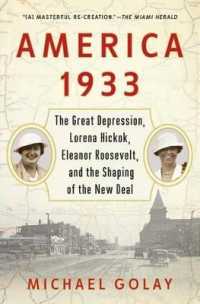- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
どの作曲家の、どの作品から聴き始めたらよいか、どんな演奏家が優れているのか、音楽に感動することの意味、演奏会を楽しむコツ、生演奏とCDの感動の差、知っておきたい音楽基礎知識と音楽史、生活の中に音楽をどう取り入れるか…第一線の指揮者として活躍する著者が、自らの音楽体験から学んだ豊富なアドバイスをわかりやすく綴った、クラシック音楽入門書の決定版。
目次
第1章 音楽とは何か
第2章 音楽のある生活
第3章 クラシック音楽への道
第4章 楽器別にクラシック音楽を楽しむ
第5章 クラシック音楽会でのマナー
第6章 CD鑑賞法
第7章 音楽の歩みと名曲
著者等紹介
大町陽一郎[オオマチヨウイチロウ]
1931年東京生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業後、ウィーン国立音楽院指揮科で学ぶ。61年に東京フィルハーモニー交響楽団の常任指揮者となる。68年にはドルトムント市立歌劇場常任指揮者としても活躍。80年には日本人として初めてウィーン国立歌劇場で『蝶々夫人』を指揮。82年からはウィーン国立歌劇場専属指揮者として活躍。現在は東京フィルハーモニー交響楽団専任指揮者、東京芸術大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
もっひぃ
6
音楽とは何か、という大前提から始まって、章がすすむにつれ段々具体的になってゆく。バランス良く書かれていて、筆者の緻密さがうかがえた。「クラシック音楽への道」と「楽器別にクラシック音楽を楽しむ」の章に知らない事がたくさん書かれていた。ヴィヴァーチェとかレントとか、ドルチェとか表情記号を覚えた。2017/03/21
N
3
クラシック入門書。1965年刊行の「クラシック音楽のすすめ」の大幅リニューアル版。鑑賞法の変化に思いを馳せて近代化の勢いをしみじみ感じました。「録音の音楽は完璧主義なので多少不安定なところがあっても生演奏のライブ感がいい」(意訳)というのはポップ音楽でも言われることですが、とりわけ古典音楽は多くのプロが深く解釈して演奏してきたことが特徴なのだと思います。作曲家のみならず、演奏家を意識するまで足を踏み入れる必要があるようです。筆者が指揮者なのでプライドと生演奏推しが強く感じられて少し笑っちゃうくらいでした。2016/06/06
yu
3
著者が指揮者なので、音楽史の部分は参考になります。しかしながら、「クラシック音楽は自宅で、または車の中でCDで聴けばいいかというと、それはコンビニで買った夕食をレンジでチンして、一人わびしく食べるのに似てみじめです。(p.8)」や「若い人が日本武道館のような大きい空間で聴くロックなどは巨大な拡声機で電気により増幅されるので、今の若者たちにはすごい音響の中で体にジーンと振動が伝わるのが受けているようです。しかし、これは音響的刺激に酔っているに過ぎないのです。(p.9)」2014/09/17
くぅ
3
まず縁のないであろうクラシックの演奏会についての本を読んでみたけど、一回ぐらい行ってみたくなった。2011/10/07
しき
2
クラシック入門編。クラシックの大まかな歴史、音楽の種類(協奏曲など)、演奏会でのマナーなどについて書かれている。例えば、モーツァルト頃までは貴族のために曲を作っていたが、ベートーヴェン以降は貴族が没落したので民衆のために曲を作っている。協奏曲はメイン楽器を他が引き立てる。交響曲は主題を元に作られる……などなど、意外に知らないクラシックの基本が学べます。本書で力を入れたのは「演奏会のマナー」だと思います。特に、イタリアオペラの、観客の拍手を巡る様々なドラマは素晴らしいです。皆様、最後は是非とも大きな拍手を。2013/01/05
-

- 和書
- 竜と悪魔