出版社内容情報
杉山城が必要とされた戦国時代とは、いかなる時代か?
内容説明
城好きなら一度は訪れてみたいと憧れる杉山城。文献には登場しないものの精密機械のような縄張りを持つこの城を、城郭研究者たちは北条氏の築城と考えてきた。だが、今世紀に入って行われた発掘調査の結果は、山内上杉氏の築城である可能性を示していた―。発掘調査によって判明した事実は何だったのか。北条氏築城説は成立しないのか。「杉山城問題」の論点を徹底検証し、縄張り研究の立場から杉山城の「謎」に挑む。
目次
第1章 城と縄張り―地面に刻まれた築城者の意図
第2章 「杉山城問題」とは何か―研究者たちの主張と立場
第3章 「杉山城問題」を検証する―北条氏築城説と山内上杉氏築城説
第4章 縄張りから考える杉山城―杉山城は織豊系城郭たりうるか
第5章 戦国前期の城を求めて―「杉山城問題」からの模索
第6章 戦国前期の縄張りを考える―比較検討の試み
第7章 比企地方の城郭群―それぞれの個性が主張するもの
第8章 杉山城の時代―戦国の城とは何だったのか
著者等紹介
西股総生[ニシマタフサオ]
1961年、北海道生まれ。城郭・戦国史研究家。学習院大学大学院史学専攻・博士前期課程修了。三鷹市遺跡調査会、(株)武蔵文化財研究所などの勤務をへて、著述業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
39
何これ、むちゃくちゃおもしろいやん!◇お城の近くの小学校に通ってたこともあり城はとても好きで、全国いろんなお城に行ってたくせに、杉山城のことは全くしらず、店頭でこの本見て「?」。文献には出てこない戦国期の名城、ここ10年で知られるようになったのか、なるほど。◇そのきっかけが、縄張りから見た年代と発掘調査の結果とのズレによる論争。これがまさに学問って感じでおもしろい。著者は縄張りを専門とする在野の研究者、その学問の立ち上がりも記されるのだが、民間学者たちが作っていくつながりは民俗学の草創期にも似て魅力的だ。2017/12/08
スー
23
34杉山城に行った際に手にしたパンフレットに発見した遺物から上杉時代に確定とあったので読むのを後回しにしてましたが読んでみると然に非ず、西股氏による反論にいちいち成程と頷いてしまいました。確かにこの時代に作られた物が出たからこの城は同じ時代に作られたとは限らないですよね、ここに捨てた人が生産されてから何年後に手に入れた可能性もあるし何年も大事に使ってた可能性もある。それに杉山城の複雑な作りを見るとやはり北条時代の方がすんなり受け入れられる感じがしました。読んでいて楽しく時間を過ごせました。2022/04/27
YONDA
18
自宅から50分ほどで行けるが、杉山城には行ったことがない。公には両上杉氏の時代に作られたとされているが、私は西股贔屓なので北条氏築城説に一票。西股氏と反対の立場にいる齋藤氏の杉山城には領主が在住していたや、門は身分指標を考えるべきだとの説はちょっと納得がいかない。どっちにしても「杉山城問題」は今後も続いて行くだろうから、西股説にたいしての反論を書いた本が読みたい。そして杉山城を訪れ、横矢掛かりを体験したい。2018/04/15
kawasaki
9
先史・古代を指向してきた考古学と、文献史学とのニッチに、在野の学問として発展してきた中世城郭研究(「縄張り研究」)。優れた構造で斯界に知られた埼玉県の名城の構築年代をめぐる議論「杉山城問題」を、「縄張り研究」畑の著者が努めて客観的に紹介するのであるが、そもそも城郭という対象についての研究史や、各種手法からのアプローチの実際などを総合的に知ることができる。「縄張り研究」を方法論・科学性を備えた学問として発展させ、文献史学や考古学と対等に議論できる位置に押し上げたいとする情熱を感じる。2021/11/12
めめんともり
6
城好きなので手に取った。敵を防ぐため、とてもよく考え設計された城がある。誰がいつ築いたのか分からない。城の設計を研究している人の考えと、城から発掘した物を研究する人の考えが食い違い論争になった。異なる手法で対象を観ることでより深く考察できるようになる好例だと思った。2021/11/16
-
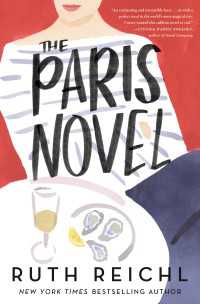
- 洋書電子書籍
- The Paris Novel
-
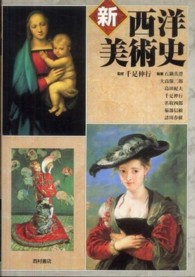
- 和書
- 新西洋美術史




