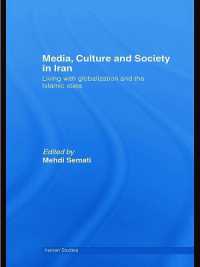出版社内容情報
古代社会をつくった交易ネットワーク。その贈与と互酬のシステムを探る!
国家誕生以前の古代において、越境的な交易関係は、文化の異なる地域や集団間でどのようにして結ばれ、いかに社会変容をもたらしてきたか。王権や国家間の外交史として語られがちな国際交易を、首長層ネットワークと威信財となったモノの動き、「海商の誕生」、東アジア海域での連鎖的で広域的な社会関係、唐物が偏重された背景などから探り、弥生時代からはじまる多様でグローバルな交易の実態を通史的に明らかにする。
プロローグ ―交易史から国際交流を考える
一 東アジア海域交易圏と倭人の首長たち
1 東アジア海域交流・交易圏をさかのぼる
2 帯方郡から邪馬台国へ
3 卑弥呼の交易
4 倭人の首長と国際交易
二 対外戦争と国際交易
1 緊迫する東アジア海域と北部九州
2 軍事と交易
三 律令国家の成立と国際交易
1 隋・唐帝国の登場と列島の南北交易
2 整理される「内」と「外」
3 国際交易を管理する
4 交易にあらわれる中心と周縁
四 海商の時代の到来
1 海商の萌芽
2 日本で活動をはじめた新羅の交易者たち
3 帰化人か漂流者か、それとも商人か
五 唐物を求める政治
1 張宝高と文室宮田麻呂
2 皇位継承と唐物
3 唐物使の登場と大宰府
六 中国と日本を結んだ商人たち
1 在唐新羅人の交易ネットワーク
2 江南海商の対日交易
3 唐滅亡と日本の交易管理の行方
七 交易がつなぐ人と地域
1 交易港と交易港の間
2 交易者と仏教
3 交易列島の南・北
4 異文化間の交易者たち
エピローグ ―中心と周縁の列島交易史
内容説明
日本列島の古代人は、海を越え、国際社会とさかんに交易を行っていた。彼らは交易を通して異文化とどう交わり、社会はいかにして変容をとげたか。東アジア海域の連鎖的で広域的な社会関係、首長層のネットワークと威信財となったモノの動き、海商の誕生と活発化、貴族たちが唐物に群がる背景などから、多様でグローバルな古代社会の実態を探り、王権や国家間の外交史として語られがちな国際交流を、交易史から通史的に捉えなおす。
目次
1 東アジア海域交易圏と倭人の首長たち
2 対外戦争と国際交易
3 律令国家の成立と国際交易
4 海商の時代の到来
5 唐物を求める政治
6 中国と日本を結んだ商人たち
7 交易がつなぐ人と地域
著者等紹介
田中史生[タナカフミオ]
1967年福岡県生まれ。早稲田大学第一文学部史学科卒業。國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期修了、博士(歴史学)。関東学院大学経済学部教授。専門は日本古代史。地域史や国際交流史の研究から列島の古代社会の多元性・多様性・国際性を解明(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ノン・シュガー 4 KoiYui(恋結)
-
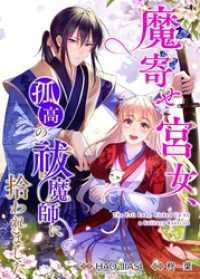
- 電子書籍
- 魔寄せ宮女、孤高の祓魔師に拾われました…