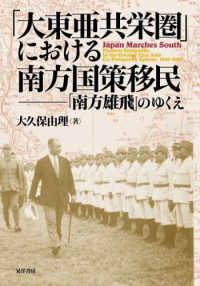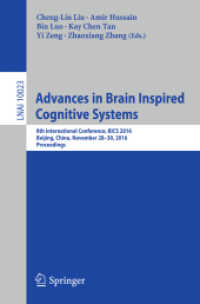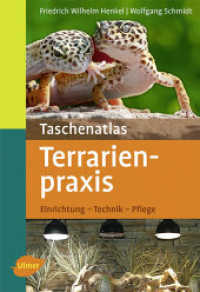出版社内容情報
日本初の近代的辞書と言われる『言海』は、明治期の日本語を映し出す鏡の役割を持っていた。編纂者・大槻文彦が凝らした配列や表記、語彙選別の苦労を丹念に読み解きながら、『言海』の真価を明らかにする。
内容説明
明治24年に完成した『言海』は、日本初の近代的国語辞典といわれる。五十音順の配列を採り入れたことでも知られ、漢語と和語とに使う活字を変えるなど、細部にわたって編纂者・大槻文彦のこだわりがみられる。大槻は、何を目指していたのか。『言海』に収録されたことばと夏目漱石、北原白秋らの文学作品を対照しながら、“日本普通語ノ辞書”『言海』の魅力と明治の日本語の姿を活き活きと描き出す。
目次
第1章 大槻文彦と『言海』
第2章 『言海』の特徴
第3章 見出し項目と語釈から『言海』をよむ
第4章 明治の日本語と『言海』
第5章 『言海』をライバル視した山田美妙『日本大辞書』
終章 『言海』の評価
著者等紹介
今野真二[コンノシンジ]
1958年、神奈川県生まれ。1986年、早稲田大学大学院博士課程後期退学。高知大学助教授を経て、清泉女子大学文学部日本語日本文学科教授。専攻は日本語学。著書は『仮名表記論攷』(清文堂出版、第30回金田一京助博士記念賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
志村真幸
1
明治期の国語辞典である『言海』を手がかりに、当時の「ふつうの言葉」を明らかにしようとしたもの。 『言海』がどのようにして編纂されたかから始まり、従来のいろは順から五十音順になった理由、発音の示し方、漢語を和語で説明している例が多いこと、カタカナ語の採用、ふりがなの使われ方などが点検されていく。 そのさきに見えてくるのは、明治期の日本語の実態である。いまの日本語と予想以上に異なるのに驚かされる。 それにしても分析の手法がたくみで、説得力もある。辞書を使った研究とは、こうやればいいのかと教えられた。2021/07/02
ハヤカワショボ夫
1
島地氏愛読の「言海」の読み方の本。空海の様々な本を読んできて、原著を読むことの大切さを感じ、「言海」も明治の言葉の遣い方を感じるために最適の本で、芥川龍之介・夏目漱石の古典を読む際に最適なガイド本となるそうです。「言海」は興味があり一度読んでみたいのですがちょっと高いな…。【図】★★2015/04/30
しいら
1
ことば自体は変わっていなくても、生活や習俗が変わると言葉の意味は変わっていく。今は当たり前のように使っている言葉も、案外早く廃れてしまうものかもしれんね。2014/11/20
KTakahashi
0
言海を調べるために読んでみた。2017/02/21
takao
0
青空文庫に辞書がほしい2016/08/15