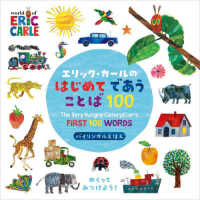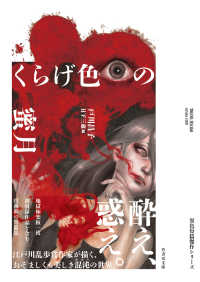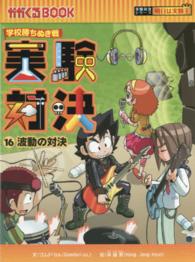内容説明
“私が私ではなくなってゆく日々”を生きる老人。そして“老い”がもたらす圧倒的現実に翻弄される介護者。互いに相手を思いやりながら、なぜケアの場は歪み、両者の関係は抜き差しならぬものになってしまうのか。複雑な感情に彩られた高齢者ケアの“親密な空間”を、老い衰えゆくことに固有の社会性として発見。柔らかく老いを支える社会制度を、介護の現場から展望する。
目次
序章 できたことが、できなくなる―“どっちつかずの人たち”の心とからだ
第1章 「できる私」へ囚われるということ―生き抜くがために自らを守る
第2章 できなくなっていく家族を介護すること―過去を引きずって現在を生きる
第3章 夫婦で老いるということ―他者に関係を開きつつ閉じてゆく
第4章 施設で老いるということ―耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶ
第5章 この社会で老いるということ―戦後日本社会のなかの“老い”
著者等紹介
天田城介[アマダジョウスケ]
1972年、埼玉県生まれ。立教大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程修了。現在、立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授。専門は社会学(福祉社会学、医療社会学)。著書に『「老い衰えゆくこと」の社会学』(多賀出版、2003年。第三回日本社会学会奨励賞受賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まいこ
1
何かを喪失していく時間、できていたことができなくなっていく過程を生きていくことは恐ろしいし難しい。 とくに夫が妻を介護するケースは、女性が自分の老いを早くに受容するのに対して夫は妻の老い衰えゆく現実が認められず、頑張らせてしまうという。そこには自分の男性性への執着もあるという。読んでいるとひたすら欝になってくるけれど不思議とこのテーマには惹かれてしまう。2014/04/22
ブラタン
1
介護職員から大学準教授にまでなる。大した人だ。それもこの本を読めば納得できる。一人一人の認知症患者の一言一言を紡んで、ここまで認知症患者の本質をつかむとは。一般の神経内科医でもできない人が多いのに。ただの出来事をそのまま書き、自分の思いを書いたのではそれは学問では無い。そこからものの本質を絞り出す作業が学問なのだと伝えたいのであろう。2012/09/16
ビアスキ
0
良かった2012/02/25
YASU
0
そろそろそういう歳になってみて初めて実感として迫ってくるもの.自分の中にそうした実感を”発見”してみたくて手に取った.本書では,夫婦の関係,施設職員との関係,さらに社会との関係から,それらが社会学的に論じられていて,なかなか奥深いものだと再認識することができた.さて,こうれからどう老いてみようか.2021/10/23
-
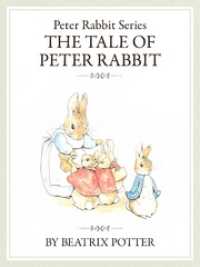
- 電子書籍
- ピーターラビットシリーズ1 THE T…