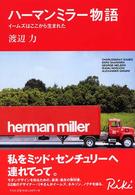内容説明
悪へと向かう人間の衝動を愛と道徳の創造力へと転じる「秘儀」とは?苦悩と歓喜の神「ディオニュソス」の精神を高らかに肯定、解放したプラトン、ニーチェの哲学、そして孤独な魂の救済を模索したリルケ、ノヴァーリス、ヘッセの文学を精緻に読解。彼ら哲人・文人の知恵の言葉とともに、生命にひそむ破壊衝動を、芸術と感覚の教育を通じて「共に生きようとする意志」に育てようとしたシュタイナー思想の核心を平易に解きあかす。
目次
第1部 不幸なる時代(軽い神秘学―「悩みの都市」の傍らで;生命にとって道徳とは何か―シュタイナーの師、ニーチェ)
第2部 「戦い」の中を生きる子どもたち(十二歳の危機―子ども、あるいは訪問者たち;内面生活のための教育―感覚教育の本質)
第3部 新しい時代、あるいは内面への旅(来たるべき教育―エーテル体をどう育てるか;内面への旅―ノヴァーリスとシュタイナー;孤独・出会い・共同体―ヘッセと他者への目覚め)
著者等紹介
高橋巖[タカハシイワオ]
東京・代々木生まれ。慶應義塾大学文学部大学院修了(美学専攻)。1957~60年、64~66年、ドイツ留学。現在、日本人智学協会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichiro Minematsu
16
リーダーシップ→4つの気質→シュタイナーとつながっての本著の再読。シュタイナー思想の中核となる「内面への旅」では、内面を掘り下げようとすると、途方もない破壊力と向き合わざるを得なくなる。その破壊力というのは悪そのものである。更に難しい(笑)2018/11/03
Koichiro Minematsu
14
シュタイナーの思想に触れたくての図書館本。人間の内なる世界と外の世界にある問題を解決するには、明確な理解ができず、やや難しい本でしたが、キーワードとしては「感覚を育てる」ということかなっと。自己を確認するだけではない、自己を超越した、自己の内部に入る内面への旅。自己の背部の世界を理解すること。出発は共に生きようとする意志。ノヴァーリスの「青い花」に続きそうです。2018/10/28
Yuji Hamano
4
シュタイナーの思想がニーチェやカントと並べて扱われる性質のものである事を知った。いまの精神世界を語っている本もかなりシュタイナーから単語を貰っている様な気もした(どちらが初めなのか、翻訳上なのかは分からないが)目があるから光がある?光があるから目がある?この議論が悪の存在に通じるなど思いもよらなかった。2015/11/02
タケヒロ
4
神秘学は、通常の学問や常識、通念の裏の概念を発想するという特性をもっている。真実は分からないのだから、発想は豊かな方がいい。我々はもともと一つの存在であったが、バラバラに分かれて個別化していった。自分が全て(世界)に関わっているという感覚が大事なのだろう。教育は「感覚」が重要。例えば歴史、地理、算数でも、国語でも、体育、歌、工作、すべて感覚教育になる。それどころか、今自分が教えている内容がどこまで子どもの感覚に伝えられるか、が重要。学校の授業がなぜ面白くなかったかがよく分かった。2014/11/24
酒井一途
3
リルケやノヴァーリス、ヘッセなど僕の大好きな作家の言葉に触れながらシュタイナーの思想を解説していく。アストラル体やらエーテル体という慣れない単語に戸惑うが、本質では見ようとしているものは近しいのではないかと感じたのでもっと知っていきたい。2013/06/08
-
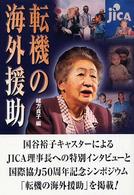
- 和書
- 転機の海外援助