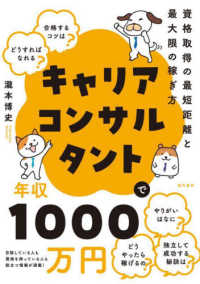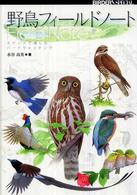内容説明
私たちが現在使っている「愛」や「性」という言葉の概念は昔から同じような意味で使われていたものではない。現代の日本人が「愛」や「性」に抱くイメージは、どのような軌跡をたどり形成されてきたのだろうか?その変容を文学や絵画などに描かれたさまざまな表現に焦点をあてて考察。時代や男女の違いによって異なる多様な恋愛観、結婚観、性愛観の文化史的意味を探る。
目次
第1部 色と人情の江戸―「性欲」以前(春画のスピリチュアリティ―「現世離脱欲」の表現;人情本と「性欲」の発見―為永春水と森鴎外;「美人」の時代―「好色」における女と男)
第2部 「貞操」と「夫婦愛」の近代―オンリーユー・フォーエヴァーの倫理(与謝野晶子の「貞操」と「処女」論;“夫婦愛小説家”としての谷崎潤一郎―「色情」から「恋愛」へ;御伽草子の夫婦の「情」)
第3部 「愛」の諸相と現代(心中の変容―『古事記』から『失楽園』まで;戦後民主主義社会と「貞操」の崩壊;高齢化社会における恋愛の将来)
著者等紹介
佐伯順子[サエキジュンコ]
東京都生まれ。学術博士。国際日本文化研究センター客員助教授等を経て、同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻教授。著書に『「色」と「愛」の比較文化史』(岩波書店サントリー学芸賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
松本直哉
21
浮世絵における男女差の希薄さ、歌舞伎の女形など女性的な男性への好み、男色への寛容、春画のポルノというよりも呪術的な意味合いなど、江戸期の性愛の話が面白く、それだけに明治以降の劇的な性愛観の変化、そして現代における同性愛への根強い偏見などを見ると、まことに隔世の感があるし、only you forever などという価値観もごく最近のものなのだとわかる。江戸期の同性愛に触れつつも、明治以降はもっぱら異性愛のみが扱われているが、谷崎の卍から中山可穂に至る同性愛文学の系譜への言及もあればもっと良かった。2025/02/01
暇人
1
日本人の根底に流れるエロスを古典などの文芸や民俗学的な風俗観測から読み解いた一冊。米などの豊穣につながることから、性に対しては大らかな気質なようだ。キリスト教思想が明治時代以降に本格的に入りこみ、廓文化が壊れていく。いい悪いは別にして趣深い。2017/03/11
なめこ
0
「恋愛」や「性愛」ないしは「性欲」という概念が登場する以前の時期の文学作品などの分析からはじまり、その後、それらの概念が時代とともにどのように移りかわってゆくのかを論じている。興味深い指摘もありつつ、全体的にちょっと視野が狭い気がする。『痴人の愛』に「フェミニズム的な意義」を見出だせる、なんて言っている部分なども、ちょっと楽観的すぎるんじゃ、っておもった。 2017/06/13
しろのやま
0
恋愛観や性愛観も当然歴史的なものであり、文学作品や絵を通してその変遷を詳らかにしている。特に為永春水『春色梅児誉美』と森鴎外『ヰタ・セクスアリス』を引いて近世から近代への過程が明らかにされているところは非常に鮮やかである。巻末に近世「色事」観と近代「恋愛」観が対比された評がある。色事のスピリチュアル性は失われていわゆる現代的倫理観が発露するのはやはり近世末から近代なのだろう。それにしても現代恋愛観を「貞操」観念の希薄化からスピリチュアル性の失われた近世色事的関係と論じているのもなるほどなあと。離婚率も上が2013/03/06
Kiu Kiu
0
とにかく明治が過渡期!非常に面白いほんだった。佐伯順子先生の本、読み続けよう!2022/04/13
-
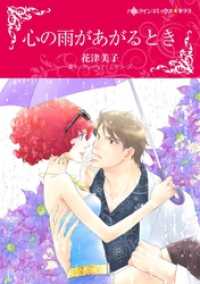
- 電子書籍
- 心の雨があがるとき【分冊】 1巻 ハー…
-
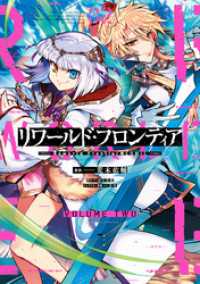
- 電子書籍
- リワールド・フロンティア@COMIC …