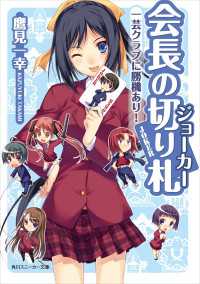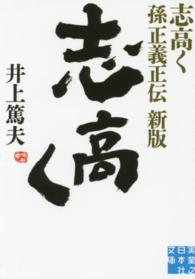内容説明
国家の権力が強力かつ中央集権的であった古代や近世に較べて、地方分権的であった中世は、村のかたちや生活も自立的で多様であった。中世の村は、どんな社会システムのもとに営まれていたのか、そしてどのように近世の村へと移行したのか。従来の研究ではとらえられなかった中世の庶民生活と村の実態を、地形・景観・暮らしをキーワードとして、考古学や環境史も視野に入れつつ立体的に復原。近世への歴史展開を明らかにする。
目次
第1章 さまざまな生業(水田と畠地;さまざまな耕地;さまざまな生産活動)
第2章 さまざまな村のかたち(中世の村落景観;山麓と乾田低地の村々;台地部の村々;低台地の村々;低湿地の村々;山海の村々;村落景観の展開)
第3章 暮らしの諸相(衣料と衣服;共食と米志向;集落と住居)
第4章 村の労働と哀楽(村の負担と定め;自然の脅威と飢饉;信仰と楽しみ)
おわりに 近世の村へ
著者等紹介
原田信男[ハラダノブヲ]
1949年生まれ。国士舘大学21世紀アジア学部教授。明治大学大学院博士後期課程退学、博士(史学)。著書に、『江戸の料理史』(中公新書、サントリー学芸賞受賞)、『歴史のなかの米と肉』(平凡社選書、小泉八雲賞受賞)など多数。村落史と食生活史を軸に、日本人の生活文化史を構想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
45
室町時代の惣村について知りたくて読んでみたが、関東地方を中心とした地域が著者の研究範囲らしく、近畿地方に多く見られる惣村についてはあまりよくわからなかった。しかし水田稲作だけでなく、狩猟や漁撈も行っている兼業農家が多い地域では浄土真宗系が多いのは、水田稲作中心の地域と地形や水源からして異なっているという指摘は興味深く感じた。また、自力救済の考えが支配的な時代は現代とは大きく異なることが改めて認識できた。農民が自ら武装して戦う様子は黒澤映画の「七人の侍」とはイメージが全く異なるのだと感じた。2022/10/26
ほっちょる
3
中世の村の研究は、古文書からみた荘園制研究が主流だが、村の生活の実態となるとアプローチがむずかしい。本書は、関東の中世の村の景観について、史料による検討を行いながらも、絵図や村落の立地等から復元を試みる。とくに村落景観の類型化では、安定的な村々は、山麓型や乾田低地型のような水田開発のしやすい地形に作られ、谷田は必ずしも普遍的でなかったとする。興味深いのは、山麓型や乾田低地型の村落を中世武士団の主流が占め、深い谷田型から湿田低地型、低台地型へと開発が進展するにともない、傍流が展開するという指摘であった。2024/07/11
15deossan
1
中世日本の村や村人(百姓)について書かれた本。労働、景観、衣食住、信仰など、詳細に解説している。江戸時代以前の百姓(農民)のことが知りたくて読んだ。昔から人民の大多数は百姓らしかったけど、メインテーマになることは少ないので、気になっていた。村とは、集落+耕地+α。近世の村との違いは、武士がいたこと、農民も武器を持っていたこと、などなど。百姓は昔から、お上の言われるがままというイメージだったが、中世はずいぶん違っていたんだなぁ。2016/03/12
井上岳一
1
中世の村に焦点を当てて、その成り立ちを詳細にレポートしている。凄く面白い。地形に応じた村の分類が素晴らしい。日本人がどういうところに住んできたかがよくわかる。分権的に生きていた中世の村の有様もよくわかる。同時に、いかに年貢に農民たちが苦しめられてきたのかも。村や共同体について興味のある人は必読。2015/07/27
mach0.9
1
読み物であるか、資料であるかとすれば、これは資料である。この資料の包括さに驚き、震えている。この本の示した、地形類型分類は、今後の僕に大きな影響を与えるだろう。読んでよかった。題材のメインは水田耕作法から、地形の利用を類型化し、さらにそれによって中世勢力の地形利用を明らかにするものである。この本の記述に本当に驚いたのは、この後に中世武士の城を読んでからである。読みあわせによって力を発揮する本というのは本当の地力を持っていると痛感する。つまり、中世武士の城を調べてみると、この本によって指摘されている、山麓湧2013/03/26